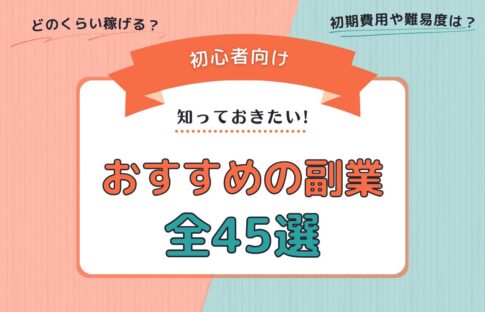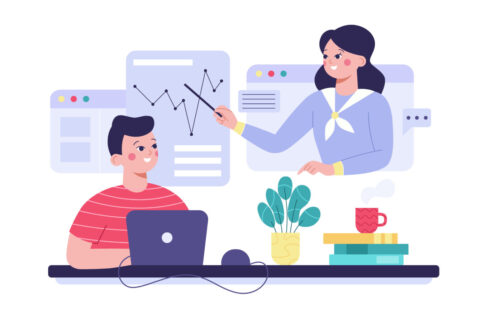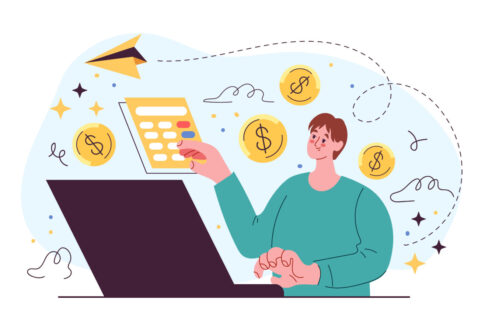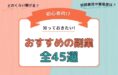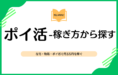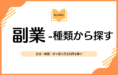ソニーや富士通、三井住友銀行など大手企業が次々と副業解禁へ舵を切り、“副業禁止”はもはや時代遅れ。それでも就業規則には罰則が残り、知らずに始めれば懲戒や解雇も。
本記事では副業禁止が違法と判断される境界線を裁判例と厚労省ガイドラインで明快に解説し、公務員・会社員別の注意点、安全に稼げるポイント活動や社内申請のコツまで網羅します。副業・ポイ活初心者でも安心して一歩を踏み出せるロードマップです。
副業禁止は時代遅れ?社会と政府の方針転換を押さえる
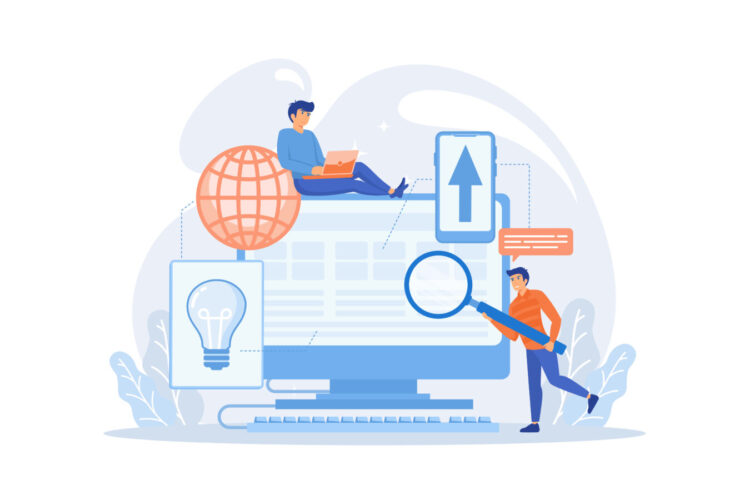
副業禁止はかつて日本企業の「常識」でしたが、政府の働き方改革や人材流動化の波を受けて急速に見直しが進んでいます。厚生労働省は2018年に「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を公表し、モデル就業規則から「許可なく他社の業務に従事しないこと」という一文を削除しました 。
その後、企業の副業容認率は2020年の49.5%から2023年調査時点で60.9%へ上昇しており、副業禁止はもはや例外的な扱いとなりつつあります 。
副業解禁は収入補填だけでなく、人材育成・イノベーション創出・採用競争力の強化といった経営メリットも大きく、逆に「副業禁止=人材流出リスク」と捉えられる時代に入りました。
政府も「新しい資本主義」の柱に副業とリスキリングを掲げ、税制や労働時間管理の整備を進行中です。
- 政府ガイドラインとモデル就業規則の改定
- テレワーク普及で時間・場所の自由度が拡大
- 人手不足と採用競争激化による人材確保戦略
以下では、歴史的背景から最新トレンドまでを整理し、読者が安全に第一歩を踏み出すための知識を提供します。
昭和〜平成初期に根付いた副業禁止慣行の歴史
昭和から平成初期にかけては、終身雇用・年功序列を前提とする日本型雇用システムが主流でした。そのため就業規則には〈許可なく他社の業務に従事してはならない〉という兼業禁止条項が当然のように盛り込まれ、違反した場合は懲戒処分の対象になるケースが一般的でした。
加えて長時間残業が前提の働き方や、企業秘密流出への懸念、労働災害時の責任分界が不透明であることなどが、副業を排除する理由とされてきました。
| 年代 | 雇用慣行 | 副業に対する姿勢 |
|---|---|---|
| 昭和30〜50年代 | 高度成長・終身雇用・社宅文化 | 全面的に禁止が主流 |
| 平成前期 | バブル崩壊後のコスト削減期 | 例外的に許可制を導入 |
| 平成中期 | IT化・成果主義導入 | 社外研修名目で限定容認 |
副業禁止が維持された背景には、労働基準法上の「労働時間通算義務」や企業別組合の強い影響力もありました。
特に製造業では技能と秘密保持を理由に厳格な競業避止義務が課され、兼業農家が賃金補填を目的に副業を希望しても許可が下りない事例が多く報告されています。こうした歴史を理解すると、現在の急速な方針転換がいかに大きなパラダイムシフトであるかがわかります 。
2018年「副業・兼業の促進に関するガイドライン」改定のインパクト
2018年1月、厚生労働省は「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を公表し、同時にモデル就業規則を改定しました。これにより、従来の「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」という兼業禁止文言が削除され、代わりに「労働者は勤務時間外において他の会社の業務に従事できる」旨が明記されました 。
改定の背景には、働き手の所得向上だけでなく、イノベーション創出や地域活性化を促す狙いがあります。ガイドラインは企業に対し、健康管理の実施、労働時間の通算把握、秘密保持契約の整備、競業避止義務の明確化といったチェックリストを提示し、原則容認・例外禁止の考え方を示しました。
- 36協定に基づく時間外労働の上限と副業時間の通算
- 医師による面接指導など過重労働者の健康管理
- 秘密保持契約・情報管理規程の整備
- 競業避止義務や利益相反防止の明文化
この改定を機に大企業だけでなく地方中小企業でも副業制度を整備する動きが加速し、官民ともに「副業は原則自由」という空気が定着しました。
コロナ禍以降に進む複業ブームと働き方改革
2020年以降のコロナ禍でテレワークが急速に普及したことは、副業解禁の流れに拍車を掛けました。リモート環境下では就業場所を問わず知見を外部に持ち帰るシナジーが評価され、企業は副業を「リスク」から「戦略」へと再定義し始めています。
例えば、日立製作所とソニーグループは2024年から社員の副業を相互に受け入れる仕組みをスタートし、先端技術領域での知見共有を図っています。
富士通も『Work Life Shift 2.0』を掲げ、300人超の社員が申請制で社外副業に挑戦中です 。さらに2024年10月には三井住友銀行が約3万人の全従業員に副業を全面解禁し、金融界にも波及しました 。
- テレワークにより副業の地理的制約が消失
- 人材育成・越境学習の一環として社外副業を奨励
- 企業間での「相互副業」やプロボノでスキルを循環
- 労働時間通算による過労・長時間労働リスク
- 機密情報の持ち出しと競業避止規程の線引き
それでも企業の副業容認率は60%を超え、社外人材の受入率も50%を突破するなど「複業ブーム」は定常化の段階に入っています 。制度面・実務面の課題を正しく理解すれば、副業はキャリアと収入を同時に伸ばす有効な手段になります。
三井住友銀行・みずほFGなど金融界の取り組み(2019〜2024年)
金融界では「情報漏えいリスク」や「長時間労働管理の複雑さ」などから副業解禁が遅れていましたが、人材確保とイノベーション創出の視点で一気に動きが進んでいます。
2024年10月に三井住友銀行(SMBC)が約3万人の全従業員へ副業を全面解禁したことは象徴的で、スポーツ指導や語学講師など非金融分野での活動を想定し、月20時間以内・承認制で運用されます。
一方、みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)は2019年10月から副業と「社外兼業」制度を同時導入。就業時間外の副業に加え、週1~2日他社に出向する兼業を認め、2021年時点で約300名が利用しています。
社外ベンチャーでの海外事業立ち上げなど実績も多彩で、「人材バリュー最大化」を掲げる同社の新人事戦略の要となっています。
| 企業 | 制度概要 | 特徴 |
|---|---|---|
| 三井住友銀行 | 2024年10月から全社員副業可 月20h上限・承認制 |
外部講師・地域貢献を推奨し 人脈拡大とスキル還元を狙う |
| みずほFG | 2019年10月導入 副業+週数日の社外兼業 |
起業も可、300名以上が利用 ベンチャー連携で新規事業を創出 |
- 高度専門人材のリスキリングと越境学習
- 社外ネットワーク拡大による新規顧客開拓
- 若手離職防止と採用ブランディング強化
- インサイダー情報管理を強化し、競業避止・守秘義務の線引きを明確化
- 長時間労働抑制のため、稼働時間を事前申告+健康チェックを必須化
- 地方金融機関でも地域副業を通じた地域創生で制度導入が増加傾向
パナソニック・リクルートなどIT・メーカー各社の最新事例
IT・製造業界ではテレワークと相性が良いため、副業解禁が早期に進みました。パナソニック ホールディングスは2022年10月に社外副業を正式制度化し、短時間勤務やフルリモートを組み合わせてボランティア・副業を支援。
グループのパナソニック オートモーティブシステムズでは2023年10月から正式運用に移行し、本業前後や週末を活用して子ども向け家具ブランド支援や地域DXプロジェクトに参画する社員が増えています。
リクルートホールディングスは2010年代半ばから副業を許可し、上長・人事承認を条件に起業やNPO活動を幅広く容認。
制度詳細は公表されていませんが、採用サイト等で「副業・兼業を通じた自律的キャリア支援」を明記しており、同社の調査によれば企業全体の副業容認率は2022年時点で51.8%に達しました。
| 企業 | 解禁時期・対象 | 主なポイント |
|---|---|---|
| パナソニック | 2022年10月正式導入 グループ全社員 |
副業時間を柔軟設定、フルリモート可 製造技術者の地域副業や起業を支援 |
| リクルート | 2016年頃から許可制 事業部長・人事承認 |
競合回避を条件に起業も容認 自己成長と社内外ネットワーク拡大を狙う |
- テレワークで生まれた移動時間を副業学習に充当
- 本業とシナジーの高い技術・デザイン案件を選ぶ
- 副業成果を社内共有しキャリア評価へ早期に反映
- 副業可否の判断基準は「競合回避」と「機密保持」が中心
- 成果物や開発コードの帰属を明記した契約書を必ず締結
- 月間労働時間ベースを選択制にするなど、柔軟な勤務制度とセットで運用
副業禁止は違法?裁判例と厚労省見解でみる境界線

「副業は就業規則で禁止されているから手を出せない…」――そう考える人は少なくありません。しかし2018年の厚生労働省ガイドライン公表以降、企業は〈原則容認〉を前提に制度を作り直す流れが加速しました。
さらに近年の裁判例では、本業に実害がない限り懲戒処分を無効とする判断が相次いでいます。違法か適法かの分かれ目は「労働時間・健康管理・機密情報・競業性」を企業が適切にコントロールできるかどうか。
本章ではガイドラインの要点と代表的判例、公務員の許可制度を整理し、副業初心者が安心して一歩を踏み出すための判断軸を示します。
- 厚労省ガイドラインの4大チェックポイント
- 副業禁止条項が無効とされた主な裁判例
- 公務員の許可制と承認されやすい副業の特徴
厚労省ガイドラインが示す「原則容認・例外禁止」
ガイドラインは「就業時間外は労働者の私的時間であり、原則副業を認めるべき」と明記し、企業が禁止できるのは、本業の遂行に著しい支障が出る場合、機密情報漏えいの恐れが高い場合、利益相反や競業に該当する場合の3条件に限定すると整理しました。さらに2022年改定では、企業側に次の義務を提示しています。
- 労働時間を通算し、週40時間・月100時間内に収める
- 医師面接指導やストレスチェックによる健康管理
- 秘密保持規程や誓約書で情報漏えいを防止
- 競業避止条項を明文化し、対象範囲を限定的に設定
ポイントは「禁止ではなく管理」に発想を転換すること。副業希望者は、自社の就業規則とガイドラインの整合性を確認し、合理的理由が示されていない一律禁止には改善を求める姿勢が大切です。
- 36協定の残業上限に副業時間を加算し、法定内に収める
- 副業開始前に仕事内容・稼働時間を共有し、透明性を高める
- 情報管理と競業避止の範囲を文書化し、誤解を防ぐ
一律禁止規定が無効とされた主要裁判例のポイント
裁判所は近年、「本業に具体的支障がない副業を理由にした処分は無効」との判断を示すケースが増えています。代表例として、運送業のドライバーが休日にアルバイトを行った十和田運輸事件では、業務成績や健康状態に問題がなく、解雇無効とされました。
また大学教授が副業として語学講師を務めた事件でも、「教育・研究活動に支障がない」として処分が取り消されています。
| 判例 | 概要 | 裁判所の判断 |
|---|---|---|
| 十和田運輸事件 | 休日に貨物運送アルバイト | 本業支障なし→解雇無効 |
| 東京都私立大学教授事件 | 無許可で語学講師などを兼務 | 教育研究に影響なし→戒告処分取消 |
| マンナ運輸事件 | 副業申請を不許可・減給処分 | 不許可理由なし→慰謝料認容 |
判例に共通するキーワードは「職務専念義務」「企業秩序」「健康安全」。副業がこれらに具体的な悪影響を与えない限り、懲戒や解雇は権利濫用と見なされやすいのが実情です。
逆に、深夜帯の長時間副業で過労運転が懸念された事案や、競合他社の役員就任など利益相反が明確な事案では、懲戒が認められています。
- 副業時間・場所・内容を記録し、本業への影響がないことを証明
- 競業避止条項に抵触しないか、事前に社内法務と協議
- 健康診断や医師面談結果を活用し、過労リスクを可視化
国家・地方公務員の副業制限と許可制の実務
公務員は国家公務員法103条・104条および地方公務員法38条により、営利企業役員や有償業務を原則禁止されています。ただし「公共性の高い活動」や「小規模不動産賃貸」「自家発電の売電」など、利害関係がなく本務に支障を与えない副業は許可を得ることで実施可能です。
許可プロセスは一般に、事前相談→申請書提出→上長承認→人事部門審査→最終許可という流れで、審査には数週間〜数か月かかる場合があります。
- 大学非常勤講師や研究助成による講演
- NPO・自治会など地域ボランティア(無報酬)
- 年間20万円以下の広告収入を得るブログ運営
ポイントは「利害関係」と「勤務時間外」の2軸で説明責任を果たすこと。営利性が高い場合でも、業務と無関係で時間管理が明確なら許可される可能性はあります。地方自治体は条例で独自基準を設けているため、必ず人事担当に最新の様式を確認しましょう。
- 申請書には副業開始日・年間収入見込み・業務内容を具体的に記載
- 許可取得後も年次報告や兼業状況の更新が必要な自治体がある
- 許可を得ないまま報酬を受け取ると懲戒処分の対象になるため要注意
副業禁止規定が残る会社・公務員のための安全な稼ぎ方

就業規則に副業禁止条項が残っている場合でも、収入源を多角化する方法は決して一つではありません。労務を提供しない資産運用やポイント活動であれば「兼業」に当たらず、許可が不要なケースが多いです。
また、社内副業や社外兼業を申請して許可を得る道もあり、就業規則そのものを改訂してもらう交渉も可能です。
本章では、投資・ポイ活といった非労務型モデル、申請フローを押さえた安全な社内外副業の始め方、就業規則改訂を促す交渉テンプレートの三つを解説します。
読者が自身の立場に合わせてリスクを抑えながら収入を増やせるよう、具体例と手順を交えて紹介します。
投資・ポイント活動など非労務型収入モデル
副業禁止規定が厳しい職場でも、労務を提供しない「非労務型」の収入源であれば多くの場合許可が不要です。代表的なのは株式・投資信託を通じた配当収入や、ポイントサイトで得られるポイント還元、フリマアプリでの不用品販売などです。
これらは勤務時間外に行い、労働時間通算の問題が発生しない点が大きなメリットです。特につみたてNISAやiDeCoは税制優遇があり、長期的な資産形成に向いています。
- つみたてNISAで毎月3万円を積立て、年平均3%の利回りがあれば20年後には約980万〜1,000万円へ成長
- 高還元クレジットカードとポイントサイトを併用すると、年間5万ポイント以上を達成しやすい
- フリマでの不用品販売は20万円以下なら確定申告不要(生活用動産扱い)
- 元手を分散し、ハイリスク商品へ集中投資しない
- 勤務先に取引報告義務がないか就業規則を事前に確認
- 収支管理アプリで所得と経費を可視化し、税務リスクを回避
非労務型収入は本業への影響が小さく、労働時間の通算義務にも抵触しにくいため、副業初心者でも取り組みやすい手段と言えるでしょう。
社内副業・社外兼業を申請するステップ別ガイド
会社が「例外的に許可制」としている場合は、正しい手順で申請すれば副業を実現できます。まずは就業規則を読み込み、申請窓口と必要書類を把握しましょう。
そのうえで、上司面談で副業の目的・シナジー・労働時間管理策を具体的に説明すると承認率が高まります。社内副業はグループ内の別部署業務、社外兼業はNPOやスタートアップへの参画などが代表例です。
- 就業規則と副業ガイドラインを確認し、禁止範囲を把握
- 副業計画書を作成(目的・業務内容・稼働時間・利益相反対策)
- 上司面談で業務影響を定量化し、健康管理策を提示
- 人事へ申請書提出後、法務・労務部門が審査
- 承認後は労働時間と成果を定期報告し、トラブルを未然に防止
- 本業とのシナジー(スキル獲得や新規事業への貢献)
- 時間管理方法(週◯時間、深夜帯不可等)
- 機密情報保護と競業避止の遵守誓約
上記フローを踏むことで、「会社への報告義務違反」「労働時間超過」「情報漏えい」の三大リスクを抑えながら副業をスタートできます。
就業規則改訂を促す交渉テンプレートと注意点
副業禁止条項が残る職場でも、社員が合理的なデータと提案を持ち寄れば改訂が実現するケースがあります。ポイントは「会社のメリット」を明示することです。
副業で得た知見を社内業務へ還元する事例や、優秀人材の定着率向上といった数値を示すと、経営層の理解を得やすくなります。
- 社内アンケートで副業希望者と離職意向の関係を調査し、数値で示す
- 競合他社が副業解禁後にイノベーション指標や売上が伸びた事例を引用
- 副業許可モデル就業規則(厚労省公開)をベースに自社向けドラフトを作成
- 感情論だけで「働き方改革だから認めてほしい」と迫る
- 上司を飛び越えて役員へ直訴し、組織秩序を乱す
- 未許可のまま副業を開始し、事後報告で既成事実化を狙う
交渉テンプレート例:「副業によるスキルアップが本業プロジェクトの品質向上につながります。具体的には◯◯ツール開発を副業先で習得し、社内DXに転用可能です。
上限時間と報告義務を遵守する前提で、就業規則の『許可無く兼業を禁ずる』条文を改訂し、申請制へ移行をご検討ください。」交渉後は議事録を残し、合意事項を文書化しておくことで、後々のトラブルを防げます。
まとめ
副業禁止は過去の慣行であり、大手各社の解禁事例が示すように潮流は「原則容認」へ。厚労省ガイドラインと裁判例を押さえれば、就業規則の壁と懲戒リスクを回避できます。
公務員は許可制、副業禁止規定が残る会社員はポイント活動や投資で収入を増やしつつ、社内申請テンプレートで堂々と一歩を踏み出しましょう。本記事を活用すれば、自分に合った副業モデルを選定し、将来資産とスキルを同時に育てる戦略を描けます。