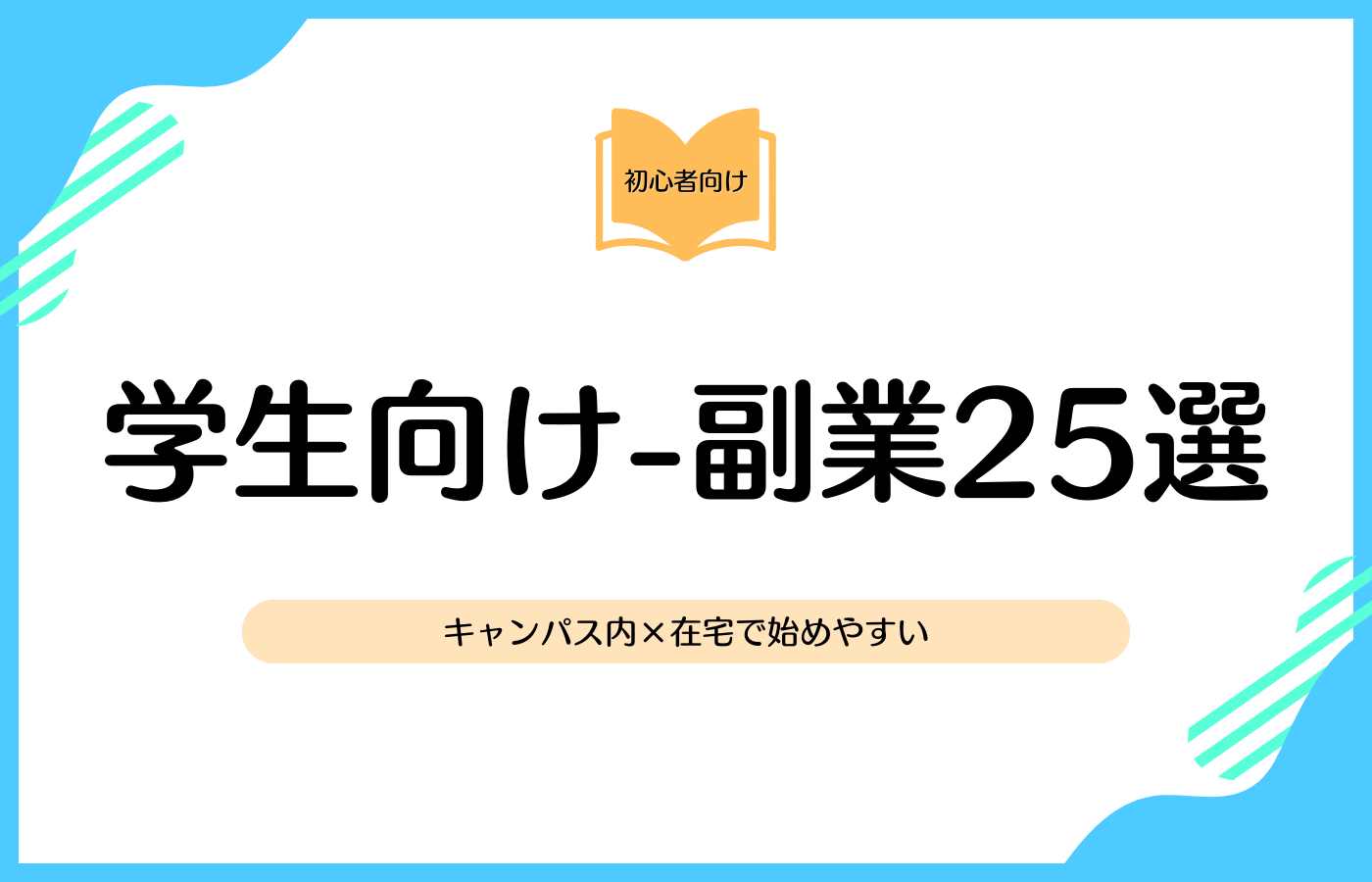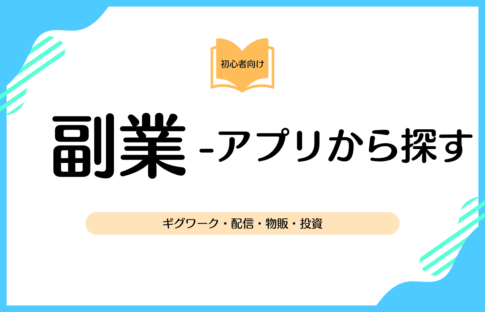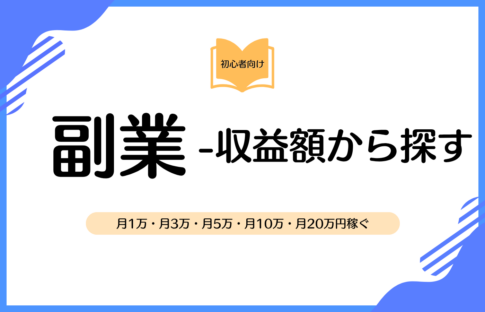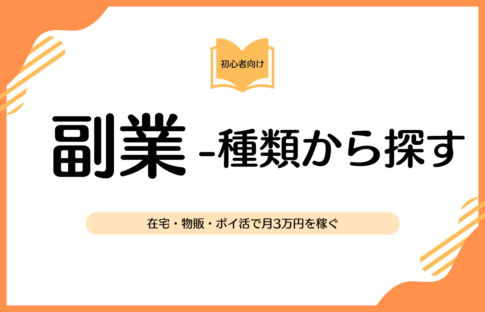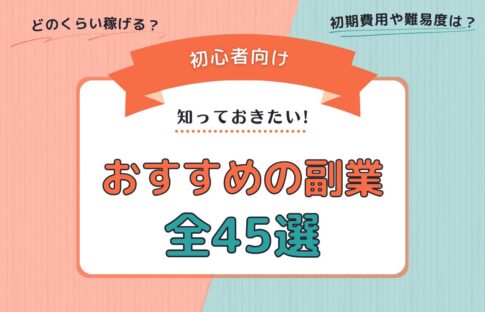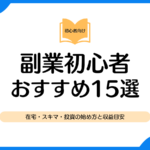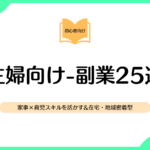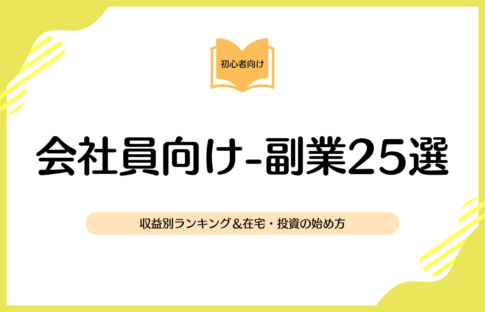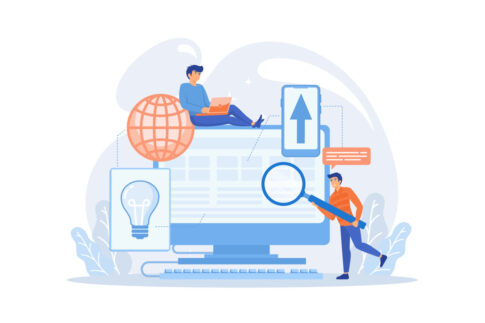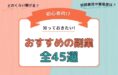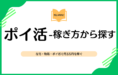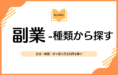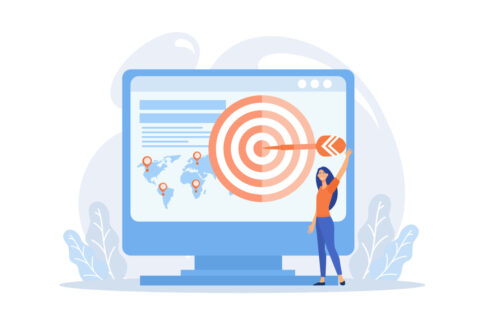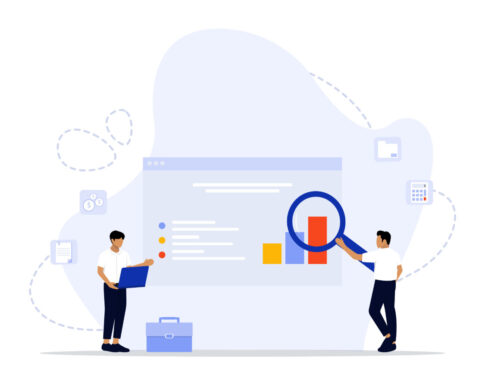キャンパス内×在宅で始めやすい、学生に人気の副業10選を厳選。TA/RA、図書館サポーター、広報アンバサダー、模試監督、オンライン家庭教師まで、募集の見つけ方・必要時間・収益目安・安全な応募と契約のポイントを整理。平日1〜2コマでも回せる現実的な両立術を、今すぐ実践できる手順で紹介します。
学生向け|副業人気ランキング10選
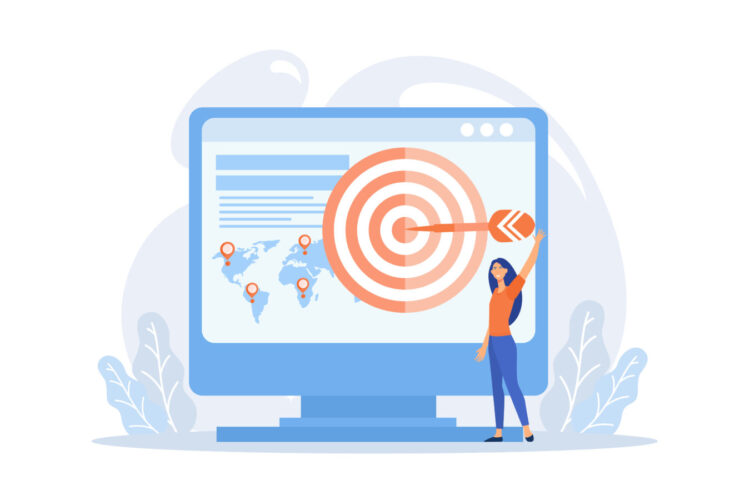
学業を最優先にしつつ「短時間・安全・経験値」を満たしやすい10種類を、学内案件→学生向け外部案件の順で並べました。
いずれも“応募窓口が明確”“成果が履歴書に載せやすい”“時間帯の融通が利く”ことを重視しています。最初は1つだけ着手し、授業や試験週に合わせて増減させると無理がありません。
下表は〈向いている人〉〈主な業務〉〈探す場所〉の早見表です。これを手元に、大学ポータルや掲示板、学内の事務窓口を毎週チェックする体制を作りましょう。
| 種別 | 向いている人 | 探す場所・導線 |
|---|---|---|
| ティーチングアシスタント | 担当科目に強み・人前で話すのが苦でない | 教務・担当教員・学部掲示 |
| リサーチアシスタント | 分析や調査が好き・正確な作業が得意 | 研究室掲示・指導教員 |
| 図書館サポーター | 静かな環境でコツコツ作業したい | 図書館カウンター・大学HP |
| PCルーム監督・ITヘルプ | PC基本操作・トラブル一次切り分けに自信 | 情報基盤センター・学内募集 |
| 学生広報アンバサダー | 写真/文章/SNS運用が好き | 大学広報室・学生ポータル |
| 留学生チューター | 語学サポート・異文化交流に関心 | 国際交流センター |
| 入試・OCスタッフ | 短期集中で働きたい | 入試課・各学部事務 |
| 大学生協(教科書販売等) | 接客/レジ対応が可能 | 大学生協の掲示・窓口 |
| 模試監督・採点 | 土日中心の単発を希望 | 予備校・模試会社の採用ページ |
| オンライン家庭教師 | 特定科目に強み・教えるのが好き | 家庭教師サービスの募集 |
- 授業と同じ曜日・時限に近い枠を選び、移動時間を最小化
- 試験週は停止できる案件を優先(短期・単発・学内案件)
ティーチングアシスタント
ティーチングアシスタント(TA)は、授業運営の補助・質疑応答・演習サポート・採点補助などを行う学内業務です。担当科目の理解が深まり、説明力やファシリテーション力が鍛えられます。
始め方は、担当教員に希望を伝えるか、学部の掲示・教務からの公募に応募します。業務は授業コマに連動するため、時間割との相性が重要です。
シラバスの進度や課題の量を事前に把握し、「試験週は別日でフォロー」「採点締切は何日まで」などの運用ルールを確認しておくと安心です。
学生相談への対応は“学修に関する範囲”に留め、個人情報を取り扱う場合は、保管場所や破棄の手順を教員と合意しておきます。
- 【探す場所】教務・学部掲示・担当教員からの案内
- 【主な業務】演習補助・採点補助・質疑対応・資料準備
- 【時間設計】授業コマ+準備/片付け分を見込む
リサーチアシスタント
リサーチアシスタント(RA)は、調査設計の補助、データ収集・整理、統計処理、文献管理、実験準備などを担う役割です。
実務で使う表計算・統計ツール・引用管理の基礎が身につき、卒論・院進にも直結します。始め方は、研究室の掲示・指導教員への相談・研究プロジェクトの公募から。依頼範囲は明確にし、データの扱い(匿名化・保存・共有)、成果物の権利(著者表示・謝辞の扱い)を必ず確認します。
作業は「下準備→処理→検算→記録」の順で定型化するとミスが減り、提出物の再現性も上がります。
アンケート回収や実験補助は短期集中になることが多いため、授業・試験とのバッティングを避けるためのカレンダー管理が必須です。
| 場面 | チェック項目 | 運用ポイント |
|---|---|---|
| 着手前 | データの機微性・匿名化・保存先 | 研究倫理と守秘の合意を文面化 |
| 作業中 | 処理手順・検算手順・ログ | 同じ手順で再現できる記録を残す |
| 提出時 | ファイル命名・版管理・締切 | YYYYMMDD_内容_v番号で統一 |
- 個人情報は最小限を原則に→不要分は速やかに削除
- クラウド共有はアクセス権限を最小化→公開範囲を定期見直し
図書館サポーター
図書館サポーターは、貸出・返却・配架・蔵書点検・学習相談ブースの運営などを行う学内業務です。静かな環境でルーティン作業に集中でき、対人対応の基礎も学べます。
募集は館内掲示や大学HPで見つかることが多く、応募時は「学期中の空きコマ」「試験週の可否」「土曜開館の対応可否」を提示できると採用後のシフト組みがスムーズです。
基本は立ち仕事もあるため、連続コマの合間に無理のない枠を選びます。延滞・破損等の対応は規程に基づくため、個別判断をせず司書・職員にエスカレーションするルールを持っておくと安心です。
- 【探す場所】図書館カウンター・大学HP・館内掲示
- 【主な業務】配架・貸出返却・ブース運営・簡単な案内
- 【注意点】規程に沿った対応・個別判断を避ける
PCルーム監督・ITヘルプ
PCルーム監督・ITヘルプは、学内のPC教室で利用者のトラブル一次対応(ログイン不可・プリンタ詰まり・ソフトの基本操作)や、機器の簡易点検、教室の開閉を担当します。
高度な開発スキルは不要でも、手順書に沿って切り分ける落ち着きが求められます。応募は情報基盤センターや学内募集から。
シフト前には「よくある質問」と「対応フロー」をプリントして席に置いておくと迷いません。セキュリティ関連(パスワード再発行等)は本人確認やルールが厳格なので、必ず職員に引き継ぐ線引きを徹底します。
| トラブル | 一次対応 | エスカレーション |
|---|---|---|
| 印刷できない | 残高/ジョブ確認→再送 | 機器故障は職員へ |
| ログイン不可 | ID/Caps確認→端末再起動 | アカウント系は職員へ |
| アプリ不具合 | 再起動→別端末案内 | ライセンス問題は職員へ |
- 事象を復唱→環境確認→再現→手順書に沿って対応
- 本人確認が必要な案件は必ず職員に引き継ぐ
学生広報アンバサダー|SNS運用
学生広報アンバサダーは、大学の公式SNSや学生向けメディアで撮影・取材・記事執筆・投稿管理を行います。
学内の出来事を外部に伝える役割のため、事前の確認・校正・著作権配慮が欠かせません。始め方は広報室の公募に応募し、簡単な制作実績(写真・記事・動画のいずれか)を提示します。
投稿カレンダーを作り、授業や試験のスケジュールと並べて“空き枠”に撮影・編集時間を確保すると無理がありません。
人物撮影は同意取得が前提、ロゴ・校章・掲示物の扱いはガイドラインに従います。成果物はポートフォリオにまとめて就活に活用できるため、版管理と権利の取り決めを残しておきましょう。
- 【作業例】取材→撮影→編集→原稿確認→投稿→効果測定
- 【注意点】肖像権・著作権・ブランドガイド順守
留学生チューター|日本語支援
留学生チューターは、日本語学習や学内手続きのサポート、生活案内、講義内容の補助説明などを行います。事前に役割範囲(学内の手続き・学習支援まで等)を明確にし、同行や個人的な依頼については“大学のルールを超えない”線引きを決めておくと安全です。
申込窓口は国際交流センター。語学力も大切ですが、相手の背景や文化差に配慮したコミュニケーションが最重要です。
情報提供は公式案内を参照し、分からない点は必ず学内窓口にエスカレーションします。活動記録を簡単なフォーマットで残しておくと、引き継ぎや評価にも役立ちます。
| 場面 | してよい支援 | 控える支援 |
|---|---|---|
| 学習 | 講義内容の補助説明・日本語練習 | 課題の代筆・不正行為 |
| 生活 | 学内制度の案内・公式窓口への付き添い | 契約の代理・私的な金銭授受 |
- 案内は“公式情報”に限定→不確かな助言はしない
- 個別トラブルは学内窓口へ同伴して引き継ぐ
入試・オープンキャンパススタッフ
入試・オープンキャンパススタッフは、誘導・受付・物品管理・試験室設営などを行う短期集中の人気案件です。春〜秋に募集が出やすく、1日単位で予定が組みやすいのが利点。
応募は入試課・学部事務からの公募が中心です。開始前に、集合場所・服装(スーツ/チノ+ジャケット等)・持ち物・休憩時間・昼食の扱いを確認し、当日は“迷ったらすぐ相談”の体制を徹底します。
構内の地図と非常口、救護・落とし物の動線を頭に入れておくと、来場者対応がスムーズです。終了後は備品チェックと片付けまでが業務の一部なので、最後まで安全第一で動きましょう。
- 【役割例】受験生誘導・受付・資料配布・教室巡回
- 【事前準備】構内地図・タイムテーブル・連絡網の確認
大学生協|教科書販売・受付
大学生協の教科書販売・受付は、春・秋の繁忙期に需要が高まる学内ワークです。業務は注文受付、在庫整理、レジ対応、袋詰めなど。
短期集中でシフトに入れるため、授業のない日や空きコマに合わせて働けます。応募は大学生協の掲示や窓口から。レジは正確さが重要なので、「金額の復唱→支払い方法の確認→レシート手渡し」の手順を固定してミスを防ぎます。
サイズや版の違いで交換が必要なケースもあるため、返品・交換規程を事前に確認しておくと現場で慌てません。荷運びが多い場合は、動きやすい服装・滑りにくい靴を選ぶと安全です。
- 金額を口に出して確認→支払い方法を確認→レシートを手渡し
- 返品・交換規程を把握→迷ったら責任者へ即エスカレーション
模試監督・採点
模試監督・採点は、土日中心の単発で組みやすく、学期の負荷に合わせて調整できるのが魅力です。主な業務は受付・受験番号チェック・配布/回収・巡回・不正防止の見回り、採点は基準に沿った機械的チェックです。
応募は予備校や模試会社の採用ページから。研修で注意点が共有されることが多いため、服装・持ち物・当日の禁止事項(私語・スマホ使用等)を事前に確認します。
会場の時間管理が業務の肝なので、集合時刻や休憩の取り方、トイレ誘導のルールをメモ化しておくと落ち着いて動けます。採点は“基準に忠実に”が最重要で、迷った答案は責任者に預ける判断が求められます。
- 【探す場所】各社採用ページ・大学掲示
- 【当日の型】受付→配布→巡回→回収→報告
オンライン家庭教師
オンライン家庭教師は、得意科目を活かして在宅で指導できる定番です。必要なのは安定した通信環境、カメラ・マイク、板書用の画面共有ツールなど。
応募は家庭教師サービスの募集から行い、履歴書には「得意単元」「合格実績(ある場合)」よりも“教え方の工夫”を具体例で書くと伝わりやすくなります。
導入は、体験授業→保護者・生徒との目標確認→教材と宿題の分量調整→次回までの学習計画、と段階を踏むと安定します。
テスト前は演習比率を上げ、平常時は基礎の定着に重点を置くなど、学期カレンダーに合わせて構成を変えましょう。
| 準備 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 環境 | 通信・カメラ・マイク・共有ツール | 事前テストで遅延/ノイズを除去 |
| 教材 | 学校準拠 or 過去問題 | 単元ごとの目標を共有 |
| 進行 | 導入→演習→振り返り | 毎回の宿題と次回の予告を明確に |
- 開始前に通信チェック→授業冒頭で今日の目標を宣言
- 振り返りメモを保護者に共有→次回の計画を見える化
始め方|募集の見つけ方

学業を最優先にしつつ安全に始めるコツは、「探す場所を固定する」「確認項目を標準化する」「応募〜初勤務までの流れをテンプレ化する」の3点です。
まず探す場所は〈大学ポータル/掲示板〉〈学内窓口(教務・図書館・国際課など)〉〈予備校/家庭教師の採用ページ〉の3本柱に絞ります。
次に、各募集で見るべき項目(勤務場所・時期・時給/謝金・業務内容・応募条件・提出物・締切)を表でチェック。
最後に、週1回の“定例スキャン”→気になる募集をブックマーク→空きコマと試験週をカレンダーで突き合わせ→応募書類を流用して申請、という導線を作ると迷いません。
下の早見表を手もとに置いて、毎週同じ曜日・同じ時間に確認する“習慣化”からスタートしましょう。
| 探す場所 | 見るべき項目 | 時短テク |
|---|---|---|
| 大学ポータル/掲示板 | 募集部署・期間・シフト・謝金・提出物・締切 | 気になる部署は“お気に入り”→毎週同時刻に確認 |
| 学内窓口(教務・図書館・国際課) | 応募要件・面談の有無・研修・守秘規程 | 窓口用の自己紹介テンプレを用意→5分で相談 |
| 予備校/家庭教師の採用ページ | 職種(監督/採点/指導)・研修・服装/持ち物 | ブックマーク→週末に新着を一括チェック |
- 大学ポータルを開く→検索語「TA/RA/学生アルバイト/臨時/公募」で横断
- ブックマーク更新→空きコマと照合→応募可否を決定
- 応募書類テンプレ(自己紹介/予定表/志望動機)を流用して申請
大学ポータル・掲示板を毎週チェック
最優先の探し場は大学ポータルと学内掲示です。学内案件は「学期スケジュールと相性が良い・移動が少ない・担当者との連携が取りやすい」という利点があり、初めての副業に向きます。
検索は“広く→狭く”の順で実施。全学ポータルで「TA」「SA」「RA」「学生アルバイト」「臨時」「公募」「学内業務」を横断→学部・研究科の掲示→図書館/情報基盤センター/国際交流センター/入試課/広報室の告知へと絞ります。
掲示は更新から日が浅い順にチェックし、「募集部署・期間・シフト・謝金・提出物・締切・問い合わせ先」をメモ化。応募前に〈授業時間割・試験週・課題締切〉と突き合わせ、無理なく続けられるかを先に判定すると、後のキャンセルを防げます。
提出物が“簡易フォーム+履修予定表”だけの募集も多いので、学期開始前に「空きコマ表(画像)」「自己紹介(200〜300字)」「得意領域」「連絡可能時間帯」のテンプレを用意しておくと、申請にかかる時間は数分で済みます。
問い合わせはメールが基本。件名は「【応募/質問】◯◯募集(学部/学年/氏名)」、本文は“要件→希望枠→提出物の有無→連絡先”の順で簡潔に。返信が遅いときは、掲示の“担当部署の窓口時間”内に電話でフォローすると早く進みます。
- 【検索語例】TA/SA/RA/学生アルバイト/臨時/公募/入試/図書館/国際交流
- 【提出テンプレ】自己紹介・空きコマ表・連絡可能時間帯・簡単な志望動機
- 毎週同じ曜日・同時刻に確認→見逃しゼロへ
- 更新日が古い掲示は“再掲”の有無を担当へ確認
教務・図書館・国際課へ相談
学内窓口は“募集の入口”であると同時に、“適性と時期の相談先”でもあります。教務はTA/SA、授業補助、入試関連の募集動向に詳しく、図書館はサポーター募集や開館シフト、国際課は留学生チューターや語学支援の募集・研修情報を持っています。
まずは5分の対面/オンライン相談枠を取り、次の3点を伝えます。〈空きコマと就業可能時間〉〈希望する業務の方向性(学内/短期/対人の有無)〉〈学期の繁忙期(試験/実習/ゼミ発表)〉。
窓口側が「この時期に募集が増える」「研修が必要」「守秘やハラスメント防止の規程がある」など、運用上の注意を教えてくれることが多く、初回でつまずくリスクを大幅に下げられます。
相談後は、案内された掲示URLや募集フォームを即ブックマークし、履修登録の確定後に再度スケジュールを擦り合わせます。
面談が必要な募集では、学生証・履修予定表・簡単な職務経歴(アルバイト歴で可)を持参し、「試験週は停止」「レポート締切日はシフト減」などの“学業優先ルール”をあらかじめ共有しておくと採用後の調整がスムーズです。
国際課経由のチューターは、支援範囲の線引き(学内手続きまで・契約代行は不可等)と連絡手段(個人LINE不可→大学メールのみ等)を確認し、両者の安全を確保します。
| 窓口 | 主な相談テーマ | 持参/準備物 |
|---|---|---|
| 教務 | TA/SAの募集時期・採点補助の規程 | 履修予定表・希望枠・連絡先 |
| 図書館 | サポーター募集・開館シフト・研修 | 空きコマ・土曜可否・学生証 |
| 国際課 | 留学生チューター・研修・連絡ルール | 語学レベル・支援可能時間帯 |
- 件名:【相談】◯◯募集の応募可否について(学部/学年/氏名)
- 本文:空きコマ・希望枠・質問事項を箇条書き→返信先を明記
予備校・家庭教師の採用ページ応募
学外で“学生歓迎”の定番は、模試監督/採点(予備校・模試会社)とオンライン家庭教師です。いずれも採用ページに最新の募集がまとまり、応募〜研修〜初勤務までの流れが標準化されています。
まずはブックマークを作り、週末に新着を一括チェック。募集を見るときは〈職種(監督/採点/校舎運営補助/オンライン指導)〉〈対象科目・学年〉〈研修の有無〉〈服装/持ち物〉〈拘束時間と休憩〉〈謝金/支払日〉〈交通費〉を確認します。
土日中心の単発を組みたい人は模試監督、在宅で平日夜に時間を作れる人は家庭教師が向いています。
応募書類は「簡易履歴(学部/学年/研究テーマ/サークル/アルバイト歴)」と「指導できる科目・得意単元・指導可能時間帯」を軸に、300〜400字の志望メモを添えます。オンライン家庭教師は通信テストが必須なので、面談前に回線とマイク・カメラを点検。
体験授業では“1回の枠で到達する小目標”を宣言し、終わりに親御さんへフィードバックを共有すると信頼が高まります。
模試監督は当日の禁止事項(私語・スマホ使用・受験票の取り扱い・時計の扱い)とタイムテーブルを事前に頭へ入れ、「受付→配布→巡回→回収→報告」の導線をメモ化しておくと落ち着いて動けます。
| 職種 | 応募前チェック | 当日のポイント |
|---|---|---|
| 模試監督/採点 | 拘束時間・服装・研修・交通費 | 集合→持ち物確認→静粛維持→報告を徹底 |
| オンライン家庭教師 | 科目・学年・面談/体験授業の流れ | 通信テスト→目標共有→振り返り共有 |
- 契約形態(雇用/業務委託)と守秘・個人情報の扱いを事前確認
- 試験週は“受注停止”のルールを共有→学業最優先で調整
時間と収益の目安|両立設計

学業を最優先にしながら無理なく続けるには、「時間の枠を先に決めて、その枠に入る副業だけを選ぶ」設計が効果的です。
おすすめは、授業のある週は平日1〜2コマ分(45〜90分)だけ、週末にもう1コマ(60〜120分)を追加する“少量固定”。
この枠で学内ワーク(TA/図書館/入試補助)や在宅の小タスク(文字起こし/データ整理/家庭教師準備)を回すと、予定変更が起きても崩れにくいです。
収益は「作業時間×時給換算」で考え、月末に金額ではなく“行動のKPI(継続率・取りこぼし率)”で健康度を確認します。
下表は時期別の運用モードと時間配分、到達の目安(あくまで試算)です。実際は学期の負荷や募集条件で上下するため、自分の時間割に置き換えて調整してください。
| 時期/モード | 時間配分(例) | 到達目安(例) |
|---|---|---|
| 授業週|通常 | 平日45〜90分×2回+週末60〜120分 | 月3,000〜8,000円相当(学内/在宅の小タスク中心) |
| 隙間拡張週 | 平日45〜90分×3回+週末90〜120分 | 月5,000〜12,000円相当(指導系/採点を加える) |
| 休暇期|短期集中 | 平日90分×3〜4回+週末120分 | 月1万〜2万円相当(入試/OC/生協など短期増枠) |
- 時間割を先に確定→空きコマに“同じ曜日・同じ時間”で固定
- 試験2週間前は新規受注を止める→既存だけ最小運転
授業週は平日1〜2コマで運用
授業のある期間は、平日1〜2コマ分の「小さな固定枠」で回すと崩れにくいです。例えば、火・木の空きコマに45〜60分ずつ、週末に60〜90分を追加する構成にして、学内の定例(図書館配架/PCルーム一次対応)や在宅の反復作業(文字起こし/資料整形/家庭教師の準備)を割り当てます。
各枠の最初と最後に“開始・終了の儀式”を作ると切り替えがスムーズです。開始は「今日の到達点を一行で宣言」、終了は「提出→記録→次回メモ」を1〜2分で残します。
移動のある案件は、授業と同じ棟・同じキャンパスで完結するものを優先し、移動時間の発生は避けます。
勤務先に伝える初期ルールは「試験週は停止」「課題締切日はシフト減」「急な補講は優先」の三点。最初に合意しておくと調整が早いです。
| 時間帯 | 割り当て例 | 運用ポイント |
|---|---|---|
| 平日空きコマ | 図書館配架/PCルーム/在宅の小タスク | 45〜60分限定→超えそうなら翌枠へ回す |
| 週末午前 | 家庭教師準備/採点/資料作り | 90分ブロック→途中で通知を切る |
- 【開始の儀式】今日の到達点を一行で宣言→作業開始
- 【終了の儀式】提出→記録→次回メモ→タイマー終了
- 空きコマの“移動しない枠”を選ぶ→同キャンパス内で完結
- 通知は授業と同じルールに→作業中はミュートで集中
テスト前は受注停止・短期集中に切替
試験2〜3週間前は、原則として新規受注を止め、既存案件も“提出期限が試験後のもの”に限定します。
停止の伝え方は、担当者へ「試験期間のため◯日〜◯日は新規不可、既存は◯日に提出」の一文を事前に共有し、引き継ぎや代替案(別日対応/分量調整)を合わせて送るのが丁寧です。
どうしても収入を維持したい場合は、入試や模試監督など“一日完結の単発”を試験のない日だけに配置し、授業や学内活動と時間帯が重ならないことを最優先にします。
在宅の小タスクは「受け取り処理」「承認待ち整理」など5〜10分で終わる作業に限定し、制作系の新規は試験後へ回します。
- 【事前連絡】停止期間・提出日・代替案を一度に共有
- 【短期集中】単発の会場業務は“試験のない日”だけ入れる
- 【在宅最小運転】受け取り・承認待ち整理だけ実行
- 時間割と試験日を確定→停止期間を宣言
- 新規募集のブックマークは維持→応募は試験後に実施
作業時間と時給換算の月次見直し
毎月の振り返りは、「金額」よりも「再現性」を見るのがコツです。まず、作業時間を“開始〜終了”で記録し、準備・移動・修正の時間も必ず足します。
次に、案件単位で「実収益÷総時間=時給換算」を出し、低いものは翌月に縮小または入替え。高いものは作業前のテンプレ化(説明用スクリプト、提出フォーマット、チェックリスト)を進めて再現性を上げます。下の表を使えば、月末30分で見直しが完了します。
KPIは〈継続率(週何日回せたか)〉〈取りこぼし率(受け取り忘れ等)〉〈学業影響(睡眠時間/出席)〉の3つに絞ると、学業と両立できているかが一目で分かります。
| 指標 | 記録方法 | 見方・次月アクション |
|---|---|---|
| 時給換算 | 案件ごとに「収益÷総時間」を計算 | 低い案件は縮小/入替→高い案件はテンプレ化 |
| 継続率 | 実施日をカレンダーに●で記録 | 週4日以上維持→届かない日は時間帯を変更 |
| 取りこぼし率 | 受け取り忘れ/締切遅延を△で記録 | 月2回以内に抑える→チェックリストを強化 |
| 学業影響 | 睡眠時間/出席の乱れを×で記録 | ×が出た週は翌週の受注を減らす |
- 収益と総時間を転記→時給換算を算出
- 良かった点/改善点を各1つ→翌月の重点に反映
注意点|法令・校則・呼び方

学生の副業・アルバイトは、「学業優先」を前提にしつつ、法令・校則・契約の呼び方を正しく理解しておくことが安全運用の近道です。まず、未成年(18歳未満)や高校生には、深夜帯の就業禁止・危険有害業務の禁止など、年齢固有のルールがあります。
次に、高校・大学ともに、校則や学内規程で「事前届出」「学業に支障が出る働き方の禁止」等が定められていることが多く、募集前に確認が必要です。
さらに、契約の呼び分け(雇用=アルバイト/業務委託=副業)を整理しておくと、適用されるルール(労働時間・休憩・残業・保険・守秘の扱い)が明確になります。
最後に、家計・税・奨学金・保険(親の扶養や学生本人の加入)との関係も早めに把握し、年間収入の見通しを立てておくと、後からのトラブルを避けやすくなります。
以下で、高校生・大学生の留意点と、契約上の呼び方の違いを整理します。
| 観点 | 確認ポイント | 主な相談先 |
|---|---|---|
| 法令 | 年齢別の就業時間・禁止業務・休憩 | 学校の就職/キャリア窓口、自治体の労働相談 |
| 校則/規程 | 事前届出の要否、試験期の就業制限 | 学年担任・教務・学生課 |
| 契約の呼び方 | 雇用(アルバイト)か業務委託(副業)か | 募集担当、キャリアセンター |
- 学期の“働ける枠”を先に決める(授業→試験→課題の順で優先)
- 校則/学内規程の届出ルールを確認してから応募する
- 契約の種類(雇用か/委託か)と守秘・個人情報の扱いを文面で残す
高校生は時間帯・校則・条例を確認
高校生が働く場合は、法令と校則の二重チェックが基本です。未成年には年齢固有の保護があり、原則として深夜帯(22時〜翌5時)の就業は避けます。
また、危険・有害な作業、酒類やたばこに関する一部の業務など、年少者に不適切な業務は就けません。学校側では、事前届出や保護者同意、試験・行事期間の就業制限が定められていることが多く、「学業に支障が出ない範囲」「学校が指定する先以外の就業は不可」等の条件が付く場合もあります。
さらに、各自治体の青少年健全育成条例では、夜間の外出や有害業務に関するルールが設けられているため、居住地域の案内ページも確認しておくと安心です。
実務では、募集前に〈校則・学年だより・進路室の掲示〉を読み、面接時に「試験週のシフト免除」「最終下校時刻と帰宅経路」を共有します。
安全の観点では、終業時刻が遅くなる連勤は避け、帰宅手段(公共交通の最終時刻や保護者の送迎)を先に確保します。
給与や休憩は採用通知で明示されるのが前提なので、口頭合意のみで働き始めず、書面やメールで条件を必ず残してください。
- 【校則】事前届出の書式・保護者同意・試験週の制限
- 【時間帯】22時以降は原則就業しない設計に→帰宅手段を先に決める
- 【業務範囲】危険・有害・年少者不適切業務は回避
- 募集前に“校則→学年指示→地域条例”の順で確認
- 面接時に「試験週の免除」と「帰宅手段」を先に共有
大学生は単位・奨学金・研究倫理に配慮
大学生は時間の自由度が上がる一方で、単位取得・奨学金・研究倫理という“学術ならでは”の制約を見落としがちです。時間配分では、履修登録後に空きコマへ定例シフトを置き、試験2〜3週間前は“受注停止”へ切替える運用が安全です。
奨学金は、種類(給付/貸与)や採用区分によって収入の扱いや報告の要否が異なり、家計の所得水準や進級要件が影響する場合があります。
アルバイト収入が直接の減額条件にならないケースでも、授業出席・成績・単位進捗が基準を下回れば継続に響くため、学期初めに条件を把握しておきましょう。
研究系の業務(TA/RA/採点補助)は、守秘・個人情報・研究倫理の遵守が必須です。データの匿名化・保存場所・アクセス権限・廃棄手順を合意し、課題の代筆や不適切な助言は行いません。
家計面では、親の税・社会保険の扶養条件(収入基準や在学要件)に触れる可能性があるため、年間収入の見通しを家族と共有しておくと安心です。いずれも「わからない点は学内窓口へ」「条件は書面で確認」を徹底しましょう。
| テーマ | 要点 | 実務のコツ |
|---|---|---|
| 単位 | 試験期前の受注停止・補講優先 | 学期初に“受注停止期間”を宣言 |
| 奨学金 | 収入・成績・進級要件の把握 | 条件をメモ化→毎学期見直し |
| 研究倫理 | 守秘・匿名化・データ廃棄 | ルールを文面で合意・版管理 |
- “試験2〜3週前は新規不可”のマイルールを相手に共有
- 奨学金・扶養は学内/家族と事前に条件確認→年間収入の目安を決める
雇用はアルバイト|業務委託は副業と表記
募集や契約の“呼び方”は、適用ルールを判断する起点になります。一般に、雇用契約で働く場合は「アルバイト」と表記され、労働時間・休憩・残業・深夜・割増賃金・年少者保護など、労働に関するルールが適用されます。
タイムカード等で時間管理され、指揮命令下で働くのが特徴です。一方、業務委託(請負・委任など)は、時間ではなく成果物/役務の完成で報酬が支払われる「副業」とされ、勤務時間の管理や割増賃金の適用は通常ありません。
納期・範囲・検収基準・修正回数・再委託可否・守秘・個人情報の扱い・報酬の支払サイト(振込日)を、必ず文面で合意しましょう。
学生に多い在宅ワーク(ライティング、デザイン、翻訳など)は、名称にかかわらず契約書を確認し、雇用(シフト制)か委託(納期ベース)かを自分の言葉で説明できる状態にしておくと安心です。
また、親の税・社会保険の扶養に影響するのは「年間収入額」等の要件で、雇用/委託の別そのものではありません。収入見通しは月次で更新し、必要に応じて家族と共有しましょう。
- 【雇用=アルバイト】時間管理・割増賃金・年少者保護が適用
- 【委託=副業】納期/検収/守秘を文面で合意→成果で報酬
- 【共通】募集要項と実態に差があれば、開始前に書面修正を依頼
- 雇用か委託か、誰の指揮命令でどの成果を出すのかを確認
- 報酬の金額・支払日・交通費・機材費の負担者を明示
- 守秘・個人情報・成果物の権利と公開範囲を合意
まとめ
まずは大学ポータルを毎週チェック→担当窓口へ相談→小さく1件だけ開始。平日は1〜2コマ、試験期は受注停止のマイルールで学業最優先に。雇用はアルバイト、業務委託は副業と認識し、校則・規程・守秘を順守します。
今週は「募集URLのブックマーク」と「作業枠の確保」まで完了し、来週1件応募を目標に進めましょう。