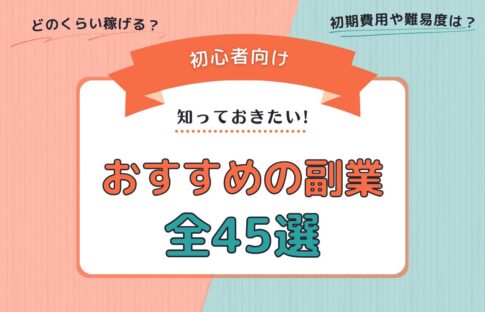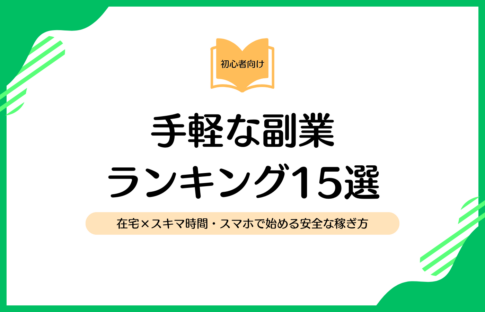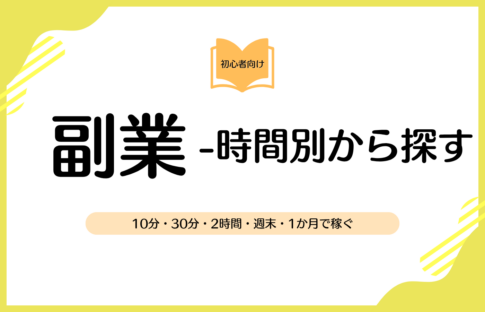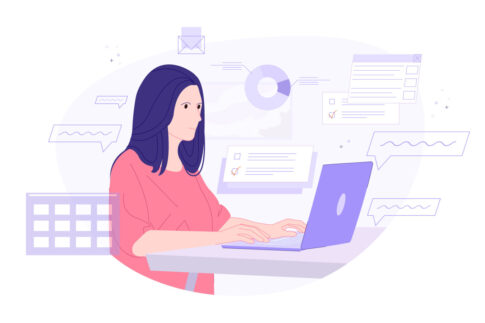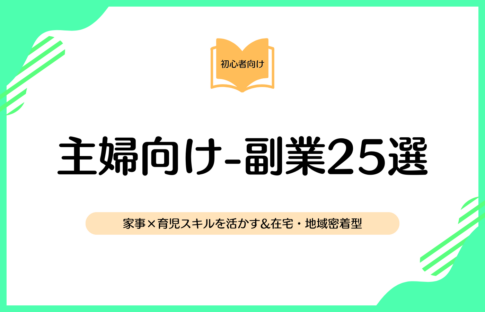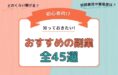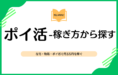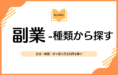副業禁止の就業規則があると収入アップは無理――そう思い込んでいませんか。本記事では副業禁止の法律根拠、企業が禁止する理由、最新裁判例や行政ガイドラインを一次情報で整理。
さらにポイ活・投資など許可不要の稼ぎ方、副業申請書の書き方、就業規則改訂の交渉術まで網羅します。読めば副業禁止下でも月5万円を目指す具体的ロードマップが手に入ります。
副業禁止の法律的根拠と会社規定の仕組み

日本企業で「副業禁止」が語られる背景には、企業が従業員の労働時間や健康を管理し、機密情報を守る責任を負う一方で、憲法22条が保障する職業選択の自由という大原則が存在するという複層的な構造があります。
2018年に公表され、2022年に改訂された厚生労働省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」は、従来の全面禁止から原則容認・例外禁止への転換を明示し、企業に対して「週40時間の法定労働時間を超える場合は36協定の上限(月45時間・年360時間※特例720時間)を守り、時間外・休日労働を合算しても単月100時間未満に管理する」ことや、医師面接指導など健康確保措置を求める。
これにより、就業規則に副業禁止条項が残っていても、合理性のない一律禁止は無効と判断される可能性が高まりました。
まずは自社の就業規則を読み込み、ガイドラインと照らして禁止理由の妥当性や改訂余地を確認することが、副業を安全に始める第一歩です。
| 法令・制度 | 副業で押さえるポイント |
|---|---|
| 憲法22条 | 職業選択の自由を保障するが、公共の福祉の範囲で制約される |
| 労働基準法38条 | 二以上の事業場で働く場合、労働時間を通算して法定内に管理 |
| 副業ガイドライン | 時間管理・健康管理・機密保持・競業避止の4領域を整備して原則容認 |
- 一律禁止条項は合理性がなければ裁判で無効となるリスクがある
- 就業規則とガイドラインを照合し、禁止根拠を具体的に確認する
- 公務員は別途、公務員法の兼業規制が適用されるため注意が必要
憲法22条と労働基準法が認める職業選択の自由
日本国憲法22条1項は「何人も、職業選択の自由を有する」と定めています。この自由は本来、兼業や副業を選ぶ権利まで含むと解釈されますが、公共の福祉の観点から一定の制約を受け得る点に注意が必要です。
例えば労働基準法38条は「複数事業場に使用される労働者の労働時間は通算して管理しなければならない」と規定し、週40時間・月100時間を超える時間外労働を防ぐ仕組みを企業側に求めています。
ガイドラインもこの条文に基づき、労働者からの自己申告制、勤怠システム連携、医師面談など健康確保措置を推奨し、企業が適切に管理できない場合のみ副業制限を認めるスタンスを示しました。
副業希望者は、まず自身の予定労働時間を可視化したうえで、上司と共有し、健康上のリスクや長時間労働にならないかを確認すると承認されやすくなります。
- 副業予定を月間シフト表に落とし込み、本業+副業の総労働時間を計算
- 深夜帯や連続勤務を避け、週1日の完全休養日を確保
- 健康診断やストレスチェックの結果を活用し、過重労働を自己管理
- 本業と副業の勤務時間をアプリで自動連携し、リアルタイムで残業上限を可視化
- 業務内容・稼働場所を上長へ文書で共有し、透明性を高める
競業避止・機密保持など企業が禁止する5大理由
企業が副業を禁止または制限する主な理由は次の五つです。第一に競業避止。同業他社で働くことでノウハウや顧客を奪われるリスクがあります。第二は機密情報漏えい。特にIT・金融・製造業では技術情報や個人データの流出が致命的打撃となるため、秘密保持契約(NDA)の徹底が求められます。
第三に長時間労働による健康障害。過労は労災や生産性低下につながるため、企業は安全配慮義務を負います。第四は企業イメージ低下。
副業先の不祥事がSNSで拡散すると本業のブランドにも影響が及びます。最後に労働時間管理の複雑化。勤怠データを通算する手間が増え、残業手当の計算が煩雑化するため、システム整備が不可欠です。
| リスク領域 | 具体的な懸念 | 主な対策 |
|---|---|---|
| 競業避止 | 同業スタートアップでの開発 | 誓約書で競業範囲を限定 |
| 機密保持 | 顧客情報の持ち出し | NDA締結・アクセス制御 |
| 長時間労働 | 月120時間残業 | 時間通算・医師面談 |
| イメージ低下 | 副業先で炎上・SNS拡散 | SNSガイドライン策定 |
| 時間管理 | 打刻データ未共有 | クラウド勤怠連携 |
- 競業範囲を「同業すべて」と過度に広げ、裁判で無効になる
- 合理的説明なく「副業一律禁止」を続け、離職率を高める
【ポイント】
- 副業希望者はリスク対策の具体策を提案すると承認されやすい
- 就業規則内の懲戒基準を明確化し、処分範囲を限定するとトラブル防止
公務員に課される法的制限と例外的な許可
公務員は国家公務員法103条・104条と地方公務員法38条によって、営利企業の役員就任や報酬を得る副業を原則禁止されています。これは行政の公平性と国民の信頼を守るための規制です。
とはいえ例外的に許可が下りるケースもあり、例えば専門分野の大学非常勤講師や自治体の地域創生プロジェクトへの参画など公益性が高い活動は承認されやすい傾向があります。
許可の目安は原則 週8時間以内・月30時間以内・平日3時間以内で、申請書には業務内容・報酬額・勤務時間帯を具体的に記載し、利害関係の有無を明示します。
申請フローは事前相談→書面提出→所属長審査→人事院(または人事委員会)審査→許可通知まで数週間~数か月かかるのが一般的です。
- 許可後も年次報告や兼業状況の更新を求められる場合がある
- 利害関係がある企業や営利性の高い投資は認められにくい
- 地方公務員は条例で基準が異なるため、必ず最新の様式を確認
- NPO・自治会活動など無報酬ボランティア
- 専門分野の講演・執筆(報酬上限内)
- 自宅太陽光発電の売電や小規模不動産賃貸
【ポイント】
- 無許可で報酬を受け取ると懲戒や刑事罰の対象になる恐れがある
- 時間・報酬・利害関係を整理し、早めに人事部門へ相談することが安全策
- 許可取得後も副業時間を記録し、勤務状況報告に備える
就業規則に副業禁止がある場合のリスクと対処法

就業規則に「副業禁止」や「許可制」と定められている企業で無断副業を行うと、けん責や減給、最悪の場合は懲戒解雇の対象となる恐れがあります。
とはいえ、裁判所は近年「本業への支障や機密漏えいといった合理的理由がない一律禁止」を無効と判断する傾向を強めています。
まずは就業規則と厚労省ガイドラインを突き合わせ、処分範囲や許可フローを確認しましょう。本節では〈懲戒リスクの実例〉〈許可制を突破する申請書〉〈許可不要の非労務型収入〉という3ステップで、安全に副収入を得るための具体策を解説します。
- 禁止条項と懲戒基準を精読し、リスクを事前に把握
- 許可制を採用している場合は、会社メリットとリスク対策を明示して交渉
- 投資・ポイント活動など労務を伴わない収入源でリスク分散
副業発覚で懲戒・減給?実例から学ぶリスク
無断副業が発覚した際に下される処分は、けん責・減給から懲戒解雇まで段階的に重くなります。たとえば運送業の「十和田運輸事件」では、年1〜2回のアルバイトが本業の成績に影響しないと判断され解雇が無効となりました。
一方、深夜帯に長時間副業を続け健康障害を発生させた事例では、減給が有効と認定されています。処分適法となるか否かは〈職務専念義務の侵害度〉〈健康リスクの有無〉〈競業・機密漏えい〉がポイントです。
| 事例 | 副業内容 | 結果 |
|---|---|---|
| 十和田運輸事件 | 貨物運送アルバイト(年1〜2回) | 解雇無効 |
| マンナ運輸事件 | 副業申請を不許可→副業強行 | 慰謝料認容 |
| 深夜居酒屋勤務 | 長時間労働・過労事故 | 減給有効 |
- 就業規則違反による懲戒処分・減給・解雇
- 社会保険や住民税の修正申告で追徴課税
- 機密情報漏えい時の損害賠償責任
【ポイント】
- 副業がバレる主因は住民税の変動、SNS投稿、勤怠データの不整合
- 処分段階は〈停止勧告→けん責→減給→解雇〉の順で重くなる傾向
- 競業要素がなくても長時間労働や情報持ち出しがあれば懲戒対象
許可制を突破する副業申請書の作り方ステップ
許可制の企業で承認を得る鍵は、会社へのメリットとリスク対策を数字と書類で示すことです。
- 就業規則を精読し、禁止理由(競業・機密・健康)の該当部分を把握
- 副業計画書に業務内容・稼働時間・報酬・社内還元スキルを明記
- 勤怠連携や自己申告フォームで時間通算方法を提示
- NDA締結、クラウドアクセス制御など情報漏えい防止策を添付
- 競業避止の線引きを副業先と本業で文書化し、上司と事前協議
- 副業先との業務委託契約ドラフト(秘密保持・競業避止条項付き)
- 本業・副業・休息日を示す月間スケジュール表
【ポイント】
- 面談では「会社への貢献」を先に示し、「自己成長」は後に述べると承認率アップ
- 承認後も月次で副業実績と健康状態を報告し、透明性を確保
- 派遣・請負契約へ切り替えられる副業は労務提供要件が緩み認可されやすい
ポイ活・投資で規定を回避する非労務型収入
就業規則の副業禁止条項は多くの場合「他社で働く行為(労務提供)」を対象にしています。労務を伴わない収入――たとえば株式・投資信託・iDeCo・つみたてNISAなどの投資利益、ポイントサイト・高還元カードで得るポイント、フリマアプリの不用品販売などは“副業”に該当せず、会社許可が不要なケースが大半です。
給与を1か所から受け取り、給与収入が2,000万円以下など一定要件を満たす給与所得者に限り、給与以外の所得(雑所得など)の合計が年間20万円以下であれば確定申告が不要とされる場合がある(いわゆる「20万円ルール」)。自営業者や給与を2か所以上から受け取る人は対象外になるため注意が必要。
- つみたてNISAで毎月3.3万円を年利3%で20年運用すると約1,094万円に成長
- ポイントサイト+高還元カードを併用し、年間5〜7万ポイント獲得も可能
- 生活用動産のフリマ販売は所得税非課税(高額品・収集品を除く)
- 暗号資産やFXは価格変動が大きく雑所得の税率が高くなりやすい
- ポイントをプリペイドカードで現金化すると課税対象になる場合がある
【ポイント】
- まず非労務型収入で月1〜3万円を確保し、申請交渉の“安心材料”にする
- 投資は長期・分散・非課税制度を徹底し、短期ハイリスク商品は避ける
- ポイントサイトは個人情報保護や換金率を比較し、安全性の高いサービスを選ぶ
副業禁止をめぐる最新裁判例と行政ガイドライン

副業を取り巻くルールはここ数年で急速にアップデートされています。厚生労働省のガイドライン改定を受け、裁判所も「合理性のない一律禁止」を無効と判断する傾向を強めました。
本章では〈裁判例の共通点〉〈ガイドラインで必ず押さえるポイント〉〈労働時間を安全に通算・管理する実務〉の3視点から、副業初心者でもトラブルを避けられる判断軸を示します。
特に労働時間通算は健康障害のリスクを下げるだけでなく、会社にとっても法令違反を未然に防げる重要なプロセスです。
- 裁判で無効となる副業禁止条項の特徴を整理
- ガイドラインが求める4領域(時間・健康・機密・競業)の管理策
- 通算管理に役立つクラウド勤怠・自己申告ツールの選び方を解説
副業禁止条項が無効となった注目判例の共通点
裁判例を俯瞰すると、会社側の処分が無効となるケースには共通する論点が三つあります。第一に本業への具体的支障の欠如。十和田運輸事件では運転手が年1〜2回だけアルバイトを行い、運行成績や安全記録に問題がなかったため解雇無効となりました。
第二は競業・機密漏えいの不在。大学教授が夜間に語学講師を務めた事例では、大学の研究内容と副業が無関係であったことが重視されています。
第三は健康管理の適切さ。副業時間が短く、睡眠や休息を確保していたと認定された場合、長時間労働には当たらないと判断される傾向です。
| 判例 | 争点 | 判断ポイント |
|---|---|---|
| 十和田運輸 | 貨物運送アルバイト | 業務支障なし→解雇無効 |
| 私立大学教授 | 語学講師兼務 | 競業性なし→懲戒取消 |
| マンナ運輸 | 副業申請不許可 | 不許可理由不明→慰謝料認容 |
- 副業に関する定義があいまいで過度に広い
- 競業範囲を「同業すべて」と抽象的に設定
- 健康・安全配慮の具体策を示さず一律禁止
【ポイント】
- 会社は「職務専念義務の侵害度」「実際の競業性」「健康リスク」を立証できないと敗訴しやすい
- 労働者側は副業時間・業務内容・休息状況をエビデンスで示すと有利
厚労省ガイドラインで押さえる労働時間・健康管理
厚労省のガイドラインは、企業が副業を容認する際に整備すべき4領域を示しています。とりわけ〈労働時間〉と〈健康管理〉は労働基準法違反を防ぐ最重要ポイントです。
具体的には週40時間・月100時間以内での時間通算、36協定の時間外上限(月45時間・年360時間など)の遵守、そして過重労働が疑われる場合の医師面接指導が求められます。
さらに、会社と労働者が「自己申告制勤怠」と「クラウド勤怠ツール」を併用するとリアルタイム管理が容易になり、長時間労働を未然に防げます。
- 副業時間を含めた週40時間・月100時間以内の通算ルールを明文化
- 自己申告フォームに「日単位」「月単位」のチェック項目を設定
- 年次健康診断結果を本人・産業医・上司が共有し、過重労働者を早期発見
- 面接指導ライン(月45時間超・月100時間近く)到達時に自動アラート
- 睡眠時間・ストレス度を可視化するウェアラブル連携
- 副業先とも共有可能な簡易勤怠CSVを定期出力
【ポイント】
- 残業上限(年720時間)と副業時間を合わせて超えないよう月初に計画を立てる
- 深夜帯(22時~翌5時)の副業は翌日の業務能率低下を招くため回避が推奨
- 産業医面談は「勤務間インターバル9時間未満」が続いたタイミングでも実施すると効果的
労働時間通算の実務と自己管理ツール活用術
労働時間通算を現場で機能させるには、会社側のシステム整備と個人のセルフマネジメントが両輪です。まず企業は勤怠システムをクラウド化し、API連携で副業先の打刻データを取り込める仕組みを導入すると効率的です。
個人側はスマホアプリやスプレッドシートで「本業+副業+休息」を一覧化し、週次でオーバーしそうなら副業時間を調整する習慣を付けましょう。
| ツール | 主な機能 | 活用ポイント |
|---|---|---|
| クラウド勤怠 | 打刻・シフト管理・36協定アラート | 副業先を外部ユーザー登録し連携 |
| セルフ勤怠アプリ | スマホでワンタップ記録 | 位置情報ONで打刻証跡を残す |
| Googleスプレッド | カレンダー連携・可視化 | 週40h・月100hを条件付き書式で色分け |
- 毎週日曜に翌週の勤務・副業予定を入力し、自動合計で超過をチェック
- 睡眠・運動ログを同じ表に管理し、健康状態を可視化
【ポイント】
- 副業先が勤怠共有に消極的な場合は、委託契約書に「労働時間提供」条項を盛り込む
- 週途中で超過が見えたら、副業タスクを成果報酬型に切り替えると調整しやすい
- 勤怠データと健康診断結果を紐づけると、会社側のリスク評価もスムーズ
副業禁止を見直す企業トレンドとキャリア戦略

厚労省ガイドラインの改定と人材確保競争の激化を背景に、大手企業の間で「副業解禁→制度ブラッシュアップ→相互副業へ」という進化サイクルが広がっています。
2024年にはソニーと日立が相互副業を試験導入し、三井住友銀行は全3万人に社外副業を解禁するなど、“全面OK”が珍しくなくなりました。
副業経験者は社外ネットワークやスキルを本業へ還元し、企業は新規事業のアイデア創出・離職防止・採用ブランディングの3効果を享受しています。
本章では、解禁事例のインパクト、就業規則を変える社内交渉術、副業OK企業やフリーランスへのキャリア戦略を整理し、読者が自分の適性に合った次の一手を描けるよう具体策を示します。
- 相互副業や全社員解禁など先進事例を比較
- 就業規則改訂を実現する4ステップ交渉術
- 副業フレンドリーな転職・独立で収入と裁量を両立
解禁を進める大手企業の最新事例と効果
副業解禁ブームの先頭を走るのは、先端技術やDXを戦略の中心に据える大手企業です。2024年2月、ソニーグループと日立製作所はAI・半導体領域で若手を交換派遣する「相互副業」を開始し、3か月で10件の新規事業アイデアを共同創出しました。
富士通はWork Life Shift2.0の一環で全社員3万5千人に副業を容認し、累計300人超が大学講師や地方DX案件に参画しています。
さらに三井住友銀行は2024年10月から月20時間上限で全従業員3万人に社外副業を開放し、多様なキャリア支援を打ち出しました。
| 企業 | 制度概要 | 得られた効果 |
|---|---|---|
| ソニー×日立 | 相互副業・3か月試行 | 先端技術ノウハウ共有、新規案件10件 |
| 富士通 | 全社員副業可、月80h上限 | 副業経験者のイノベ案提出率3倍 |
| 三井住友銀行 | 月20h・雇用契約可 | 離職意向12%→8%に低下(社内調査) |
- 外部スキル流入で新事業スピードが加速
- 社員のエンゲージメント向上で離職防止
- “副業OK”を掲げることで採用競争力が強化
【ポイント】
- 解禁後は勤怠システム連携と秘密保持研修をパッケージ化すると運用が安定
- 相互副業は競合を避け、補完関係の企業同士で成功しやすい
就業規則改訂を促す社内交渉テンプレート
「自社はまだ副業禁止…」という場合でも、数値と成功事例を武器に就業規則の見直しを働きかけることは十分可能です。交渉の鍵は、データ、他社事例、具体的ドラフトの3点をセットで提示することにあります。
- 社内アンケートで「副業希望率」と「離職意向率」を調査し、関連を数値化
- 競合や取引先の解禁事例を示し、採用ブランディングの機会損失を可視化
- 厚労省モデル就業規則をベースに、自社向け副業規程ドラフトを作成
- リスク対策(勤怠連携・NDA・競業避止範囲)を付属資料で提案
- パイロット運用→評価→正式改訂という段階的ロードマップを提示
- 副業解禁で離職率▲4pt、新規事業提案率×2を期待
- 勤怠API連携とNDA運用でリスクを最小化
【ポイント】
- 提案は「組織メリット→リスク低減策→小規模試行」の順で構成すると通りやすい
- 経営層には数値インパクト、現場管理職には運用フロー簡素化を訴求
- パイロット対象にイノベーション部門や若手リーダー層を選ぶと効果が見えやすい
副業OK企業へ転職・フリーランスという選択肢
どうしても社内で制度改訂が進まない場合、キャリアの軸足を副業フレンドリーな環境へ移すことも有効です。近年、求人サイトでは「副業可」「リモート副業可能」などのタグが急増し、IT・Web業界だけでなく製造、金融、行政ベンチャーでも募集が広がっています。
転職時は〈副業申請フロー〉〈時間上限〉〈競業範囲〉の3点を必ず確認しましょう。フリーランス型キャリアを選ぶ場合は、エージェント経由で月単価案件を確保しつつ、クラウドソーシングでスポット業務を受けるハイブリッド型が安定しやすいです。
- 求人数調査では「副業可」掲載件数が3年間で2.7倍に増加(大手転職サイト調べ)
- 副業OK企業は週3正社員やジョブ型人事とセットで裁量が大きい
- フリーランスには業務委託契約の交渉力と確定申告の知識が必須
- 競業避止期間とペナルティの有無
- 副業時間上限と申請レスポンスの速さ
- 報酬形態(成果報酬・時給・月額固定)
【ポイント】
- 副業OK企業へ転職後もスキル棚卸しを継続し、年1回報酬交渉の材料にする
- フリーランスはキャッシュフロー管理と社会保険の選択が生命線
- キャリア戦略の最終目標を「収入最大化」か「裁量・自由度重視」かで明確にすると意思決定しやすい
まとめ
副業禁止でも道はあります。法律・裁判例で境界線を知り、非労務型収入でリスクなく稼げます。さらに許可制を突破する申請術と就業規則改訂の交渉術を実践すれば、安定収入とキャリア拡大を両立可能。
大手企業の解禁トレンドを味方に転職やフリーランスも視野へ。本記事を手元に、今日から具体的な一歩を踏み出しましょう。