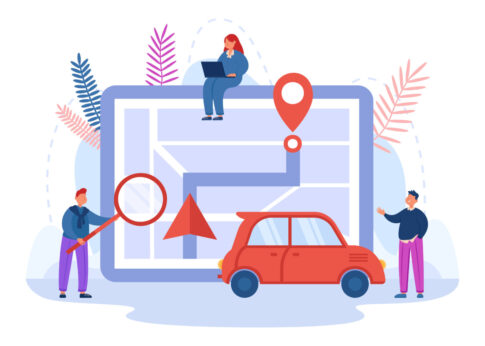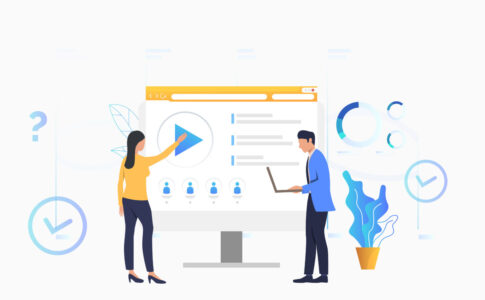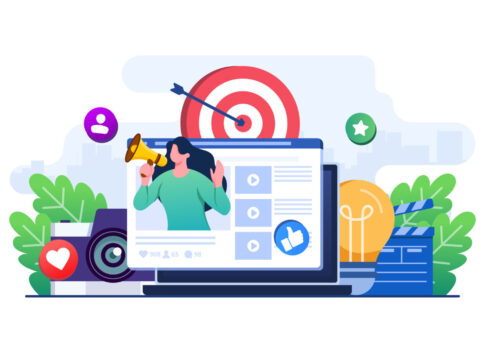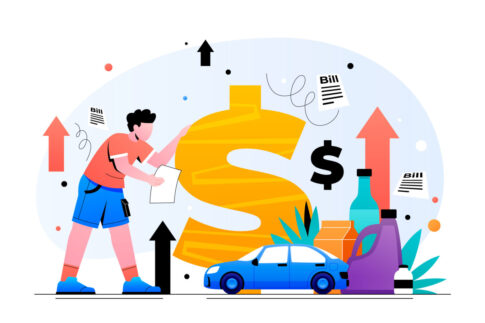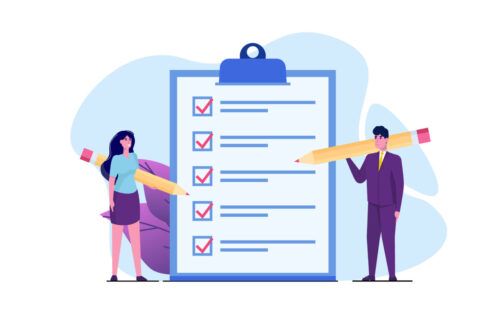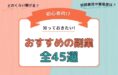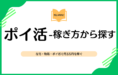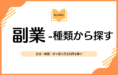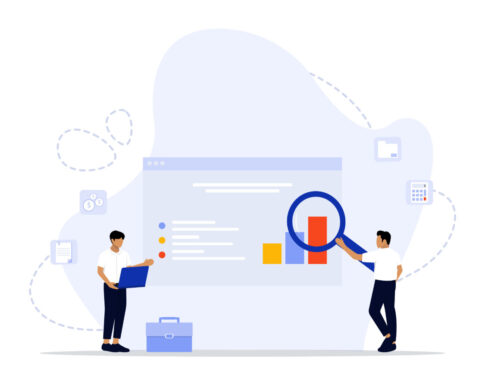「ETCマイレージは終了した?」という疑問に一次情報で答えます。全国一律の終了ではなく、終了・対象外は一部路線(阪神はポイント付与・還元額利用とも終了、名古屋・神戸市道路公社はポイント付与のみ終了〔還元額の利用は継続可〕 など)。
本記事では“何が続き、どこが終わったか”を整理し、公式の確認手順、残ポイントの扱い、今後の運用のコツまで実務目線で解説します。
『終了』は本当?公式発表で確認する基本

「ETCマイレージは終了した」という情報は、結論から言うと誤解が多いです。制度そのものは継続しており、終了・対象外という話の多くは“特定路線でのポイント付与が終わった(またはもともと対象外)”という事実に由来します。
たとえば、阪神高速はポイント付与が終了、名古屋高速もポイント付与が終了、神戸市道路公社はポイント付与を終了しつつ、還元額(無料走行分)の利用は継続可能です。
一方で、NEXCO3社や本州四国連絡高速などは従来どおり参加しており、マイレージ登録→対象路線の走行でポイントが貯まります。
まずは「制度全体は継続」「終了は路線単位のポイント付与が中心」という2つの軸で整理しましょう。
次に、一次情報(公式サイトのお知らせやQ&A)を確認し、利用中の路線が〈ポイント付与あり/なし〉〈還元額の利用可否〉のどちらに該当するかを特定します。
| 観点 | 確認ポイント | 実務メモ |
|---|---|---|
| 制度の継続性 | ETCマイレージ自体は継続 | “終了”報道は多くが路線限定の話 |
| 路線ごとの扱い | ポイント付与の有無/還元額の利用可否 | 同じ地域でも事業者により運用が異なる |
| 一次情報 | 公式サイトのニュース・Q&A | 路線名+「ETCマイレージ」で検索→確認 |
- 制度自体は継続→“終了”は主に特定路線のポイント付与
- 還元額の利用だけ継続する路線もある
- 最新情報は必ず公式サイトで確認する
全国は継続・終了は一部路線のみ
全国一律で「ETCマイレージが終わった」わけではありません。参加事業者(NEXCO東/中/西日本・本州四国連絡高速など)は継続しており、対象路線をETCで走る限り、ポイントが貯まり、還元額(無料走行分)へ交換できます。
混乱が生じやすいのは“例外”の存在です。たとえば、阪神高速ではポイント付与が終了しています。名古屋高速もポイント付与が終了しています。
さらに、神戸市道路公社ではポイント付与を終了した一方で、還元額の利用は引き続き可能という運用です。
つまり、「終了」という言葉を見聞きしたら、①どの事業者・路線の話か、②ポイント付与の終了なのか、③還元額の利用は続けられるのか、の3点を切り分けることが重要です。
副業・ポイ活目線では、普段利用する路線の扱いを正確に把握し、ポイントが付く路線で“計画的に乗る”、付かない路線では“他割引やクレカ還元を組み合わせる”という運用に切り替えるのが合理的です。
- 「全国で終了」と誤認→実際は路線単位での終了が中心
- “付与終了”と“還元額の利用継続”の区別がついていない
- 参加事業者と非参加事業者を混同してしまう
最新お知らせとQ&Aの確認手順3ステップ
公式の最新情報は、次の順序で確認すると漏れがありません。まず、ETCマイレージの公式サイトにある「お知らせ」や「Q&A」を開き、運営主体(NEXCO3社+本四高速)からの共通案内を把握します。
次に、利用中の各道路事業者(例:名古屋高速、神戸市道路公社など)の公式サイトを必ず確認し、ポイント付与終了や運用変更の発表日・適用開始日をチェックします。
最後に、会員マイページの「保有ポイント」「還元額」「事業者別の履歴」を見て、実際に自分の勘定がどう反映されているかを確認しましょう。
特に“付与終了→還元額は利用可”タイプの路線では、保有ポイントの交換期限や自動還元の設定状況を見落としがちです。
締切を超えるとポイントが失効する可能性があるため、月次のモニタリングを習慣化しておくと安心です。
【確認手順】
- ETCマイレージ公式の「お知らせ・Q&A」を確認→制度全体の方針を把握
- 利用路線の「公式サイト・ニュース」を確認→路線固有の終了・継続情報を確認
- 会員マイページで「保有ポイント・還元額・履歴」を確認→反映状況と期限を点検
- “発表日”と“適用日”を必ず控える
- ポイント交換の期限をカレンダー登録
- 自動還元の設定有無を月初に再確認
参加事業者と対象道路の見分け方
見分け方の出発点は、「誰(どの事業者)の道路を走るか」です。参加事業者(NEXCO東/中/西日本・本州四国連絡高速など)の管轄路線は、従来どおりポイント付与の対象です。
一方、もともと参加していない都市高速や、ポイント付与を終了した路線では、ポイントが付かない(または還元額のみ利用可)という扱いになります。
公式サイトには〈ポイントが付く道路〉〈還元額のみ使える道路〉の区分一覧があり、使える・使えないを事業者別に確認できます。
実務では、毎月よく通るルートを「NEXCO系か/都市高速系か」に分け、前者では平日朝夕割引などマイレージ連動のメリットを極大化、後者ではクレカ還元や各社の独自割引を組み合わせる、といった使い分けが有効です。
経費精算の観点では、明細の事業者名を月次で集計し、マイレージの対象比率(NEXCO比)を把握しておくと、ポイ活の改善余地が見えてきます。
| 区分 | 代表例 | 扱いの目安 |
|---|---|---|
| 参加(ポイント付与あり) | NEXCO東・中・西、本州四国連絡高速 など | ポイント付与+還元額利用が基本 |
| 付与終了(還元額は可の例あり) | 名古屋高速、神戸市道路公社 など | ポイント付与は終了/還元額は利用可のケースあり |
| 非参加(対象外) | 都市高速の一部(例:阪神高速 等) | ポイント付与なし(独自割引や他手段でカバー) |
- 参加路線→平日朝夕割引や自動還元を活用
- 非参加/付与終了路線→クレカ還元や独自割引を併用
- 毎月の走行実績を事業者別に可視化→最適化を継続
終了・対象外の主な路線を整理
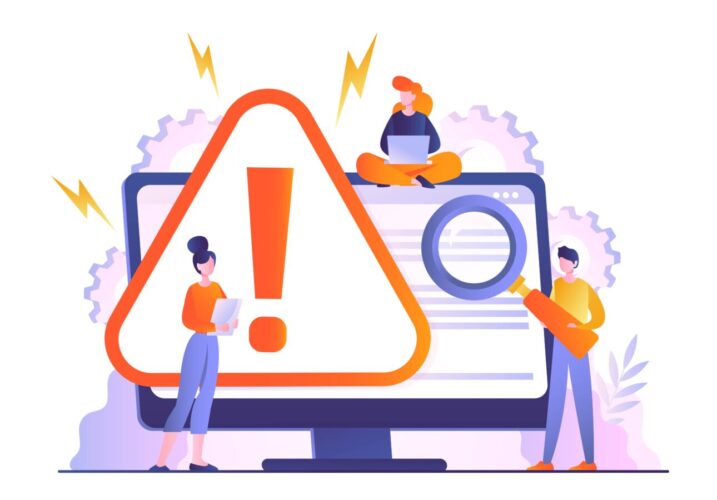
「ETCマイレージは終了した」という話題の多くは、制度全体ではなく“路線ごとの取扱い”に由来します。
本章では、誤解が生まれやすい主要3路線(阪神高速/名古屋高速/神戸市道路公社)を整理します。結論として、阪神高速はポイント付与も還元額の利用も終了しています。
一方で、名古屋高速はポイント付与のみ終了、還元額は引き続き利用可能です。神戸市道路公社もポイント付与が終了しましたが、還元額の利用は継続できます。
副業・ポイ活の観点では、普段使うルートが「ポイント付与あり」「付与は終了だが還元額は使える」「完全に対象外」のどれかを見極め、乗る時間帯・ルート・決済の組み合わせを最適化することが重要です。
月初に路線別の方針を決め、月末は残ポイント・還元額の消化状況を確認する運用にすると、取りこぼしが起きにくくなります。
| 路線 | 現在のステータス | ポイント |
|---|---|---|
| 阪神高速 | ポイント付与終了/還元額利用も終了(=ETCマイレージ対象外) | マイレージの恩恵なし→他手段で最適化 |
| 名古屋高速 | ポイント付与終了/還元額は利用可 | 保有ポイントは還元額に交換→対象路線で消化 |
| 神戸市道路公社 | ポイント付与終了/還元額は利用可 | 保有ポイントの有効期限に注意→計画的に交換 |
- 付与あり→“乗るほど貯まる”前提で回数・金額を最大化
- 付与終了/還元可→ポイントは早めに交換→対象路線で消化
- 完全対象外→クレカ還元や別割引の活用に軸足を移す
阪神高速は対象外・ポイント付与なし
阪神高速は、ETCマイレージのポイント付与がすでに終了しており、還元額(無料走行分)の利用も終了しています。そのため、現在はETCマイレージの観点での“貯まる・使える”メリットは受けられません。
過去に付与されたポイントや還元額が残っていた場合も、阪神高速での充当はできないため、実務上は「マイレージ対象外の路線」と割り切って運用を組み立てるのが安全です。
よくある間違いは、家族や社内の別カードに切り替えれば付与対象になると考えてしまうことですが、路線が対象外である以上、カードを変えても付与は発生しません。
運用の切り替えとしては、ETCマイレージを狙うのではなく、交通系クレジットカードの還元率や、所要時間・燃費・有料区間の短縮など“別の実益”を優先するのが現実的です。
走行データを月次で振り返り、阪神高速の利用が多い場合は、NEXCO管轄区間への代替ルートの可否や、移動時間の平準化(混雑回避)で総コストを抑える方針に切り替えましょう。
- カードを変えれば付与される→路線が対象外なら付与なし
- 還元額は使えるはず→阪神高速では利用終了
- 家族・社用のカード合算で解決→会員間の移動・合算は不可
名古屋高速はポイント付与が終了済み
名古屋高速では、ETCマイレージの“ポイント付与”が終了しています。つまり、名古屋高速の走行で新たにポイントは貯まりません。
一方で、すでに保有している還元額(無料走行分)は、名古屋高速を含む対象路線で引き続き利用できます。
実務のポイントは、保有ポイントの扱いです。ポイントは一定の有効期限内に還元額へ交換しなければ失効するため、期限管理(年度末単位など)を徹底しましょう。
運用上は、名古屋高速の利用が多い月でも、出発・到着前後のNEXCO区間をうまく組み合わせると、還元額の消化や他割引(平日朝夕など)の適用が狙えます。
家計・経費の観点では、名古屋高速分は“付与なし・還元のみ消化可”として集計し、対象区間と非対象区間の比率をダッシュボード化しておくと、翌月以降のルート最適化に役立ちます。
名古屋高速に関する“終了”の情報を見かけたら、それが「ポイント付与の終了」を指しているのか、「還元額の利用停止」まで含むのかを切り分けることが大切です。
- 新規付与はなし→保有ポイントは期限前に交換
- 還元額は対象路線で引き続き利用可→消化ルートを設計
- NEXCO区間を組み合わせ→自動還元や他割引も活用
神戸市道路公社は付与終了(還元は可)
神戸市道路公社でも、ETCマイレージの“ポイント付与”は終了しています。ただし、付与終了後も、還元額(無料走行分)の利用は継続可能です。
このため、残っているポイントは有効期限内に必ず還元額へ交換し、対象路線で計画的に消化しましょう。
運用面では、神戸市道路公社区間の比率が高い方ほど、NEXCO区間と組み合わせた経路設計や、平日朝夕の時間帯設計で“還元額を使い切る”動線を作るとムダがありません。
月末が近い時期は、付与・交換・反映のタイミングがずれやすいため、交換から消化までのリードタイムを確保しておくと安全です。なお、還元額での無料走行分には新たなポイントは付きません。
家族・社内の複数カードで残高を寄せ集めることもできないため、会員単位で「いつ交換して、どの路線でいつ消化するか」を月次で決めておくと、管理の手戻りを減らせます。
- ポイントは早めに交換→還元額は引き続き利用可
- 還元額の消化ルートを先に決める→月末の駆け込みを避ける
- 無料充当分に新規ポイントは付かない→家計簿上は“翌月の値引き”で管理
継続路線と制度変更への備え方

「ETCマイレージは全国で終了した」という誤解が広まりがちですが、参加事業者(例:NEXCO各社・本州四国連絡高速など)が管轄する多くの路線は継続しています。
一方で、都市高速など一部ではポイント付与が終了、あるいはもともと対象外というケースがあります。そこで重要になるのが“制度変更への備え”です。
まず、毎月の走行ルートを〈NEXCO系(付与あり)/付与終了・対象外〉に分け、付与があるルートではマイレージを軸に、対象外ではクレジットカード還元や各社の独自割引を軸に最適化します。
次に、マイページで自動還元の設定・残高・ポイントの有効期限(ポイントが付いた年度の翌年度末まで)を月初に確認し、必要に応じて手動交換も計画します。
最後に、公式サイトのお知らせやQ&Aを定期チェックし、路線別の運用変更(付与終了・交換単位の見直し等)を把握しましょう。
| 観点 | 基本 | 運用のコツ |
|---|---|---|
| 路線の継続性 | NEXCO等は継続/一部都市高速は付与終了・対象外 | 月初に〈付与あり/なし〉をルート単位で仕分け |
| 残高管理 | ポイントは翌年度末が有効期限 | 自動還元+手動交換で失効リスクをゼロに |
| 情報更新 | 公式のお知らせ・Q&Aで確認 | 「発表日→適用日」の時差を必ずメモ |
- ルートを〈付与あり/なし〉で二軸管理
- 月初に自動還元・残高・期限を点検
- 公式の運用変更は“発表日”と“適用日”を控える
NEXCO等の継続路線と利用の基本
NEXCO各社や本州四国連絡高速など、継続参加の路線では、登録済みETCカードでの支払額(他の割引適用後の実支払額)に応じてポイントが貯まり、所定の単位で還元額(無料走行分)へ交換できます。
登録自体は無料で、マイページ・自動音声・郵送のいずれかで各種変更や交換が可能です。平日朝夕割引などの別制度とは“併用の関係”になります(割引の適用可否は各制度ルールで判定、マイレージのポイント自体は割引後金額に付与)。
実務では、よく使うインターチェンジと路線を一覧化し、NEXCO系の比率が高い人ほど「自動還元ON+手動交換の併用」「平日朝夕の時間設計」「月末の残高チェック」をセットで運用すると取りこぼしを防げます。
対象外の都市高速を多用する人は、マイレージ狙いよりも、移動時間・燃費・クレジットカード還元など“別の得”を優先し、NEXCO区間が絡む日だけマイレージ活用を強める、という切り替えが有効です。
| 場面 | 基本アクション | ヒント |
|---|---|---|
| 日常利用 | 自動還元をON/月初に残高と期限確認 | 付与が見込める月は手動交換もセット |
| 通勤・出張 | 平日朝夕の“時間帯内通過”を計画 | 渋滞や工事でずれないよう余裕を確保 |
| 対象外路線多め | クレカ還元・独自割引を優先 | NEXCO区間と組み合わせて還元を消化 |
- 対象外路線で“貯まる前提”の計画を立ててしまう
- 自動還元だけに任せ、期限前の端数を失効させる
- 平日朝夕の時間ずれ→回数や割引の取りこぼし
ポイント有効期限と自動還元の確認
ポイントの有効期限は「ポイントが付いた年度(4月〜翌3月)の翌年度末まで」です。たとえば6月に付いたポイントは“翌年度の3月末”が期限。
期限管理は月初のルーチンにして、残ポイントを〈自動還元の到達見込み/到達しない端数〉で分けて考えると失効を防げます。
自動還元サービスをONにすると、所定の交換単位に達した時点で、毎月20日に自動的に還元額へ交換され、当日以降の走行から充当されます(交換単位は事業者により異なるため、マイページの案内で確認)。
一方、端数や到達見込みが低い月は、期限が迫る前に手動交換へ切替えるのが安全です。自動と手動は併用可能なので、基本は自動、年度末前だけ手動で微調整、という運用にすると無駄が出にくくなります。
交換後の還元額は現金化不可・会員間移動不可のため、翌月の経路を“消化しやすい路線”へ寄せる計画も併せて行いましょう。
| 項目 | 内容 | 注意点・コツ |
|---|---|---|
| 有効期限 | 付与年度の翌年度末まで | 月初に残高と期限を確認→端数は手動交換 |
| 自動還元 | 毎月20日に所定単位へ自動交換 | 単位は事業者で異なる→マイページで確認 |
| 手動交換 | マイページ/自動音声/事務局 | 年度末前は“端数の掃除”に有効 |
- 月初:残高・期限・自動還元のON/OFFを点検
- 月中:到達見込みをチェック→端数は手動交換候補
- 月末前:還元額の消化ルートを先に確保
割引制度との関係整理と注意点
マイレージは“ポイント付与の仕組み”、平日朝夕割引や深夜割引・休日割引は“通行料金の割引制度”です。原則として、通行料金に適用される割引は制度ルールに従い、重複する場合は最も有利な割引が適用されます。
マイレージのポイントは、こうして決まった“割引後の支払額”に対して付与されます。このため、同じ走行でも、割引の適用有無によってポイント付与額は変化します。
また、平日朝夕割引の回数カウントや還元額付与はETCカードごとに管理され、複数カード間の合算はできません。
都市高速など“付与終了・対象外”の路線を走った場合、その区間はポイントが付かない(あるいは還元額の利用のみ可)ため、NEXCO系区間と組み合わせる、時間帯を調整して割引適用を狙う、といった“経路と時間の設計”が実額を左右します。
運用では、走行明細で適用割引と付与ポイントを月次で照合し、〈割引適用→ポイント減〉でも総支払額が下がっているかを確認しましょう。
| 観点 | 整理 | 実務ヒント |
|---|---|---|
| 割引の適用 | 重複時は最も有利な割引が適用 | 割引後の支払額に対してポイントが付与 |
| 回数管理 | 平日朝夕割引はカードごとにカウント | カード分散は非効率→可能なら1枚に集約 |
| 対象外区間 | 付与なし/還元のみ可の路線もある | NEXCO区間と組み合わせ→還元消化を計画 |
- 割引とポイントは“別物”→割引後金額にポイントが付く
- カード間の合算不可→分散は取りこぼしの原因
- 対象外区間の多用時は、クレカ還元や独自割引で補完
最新情報の確認手順と運用更新
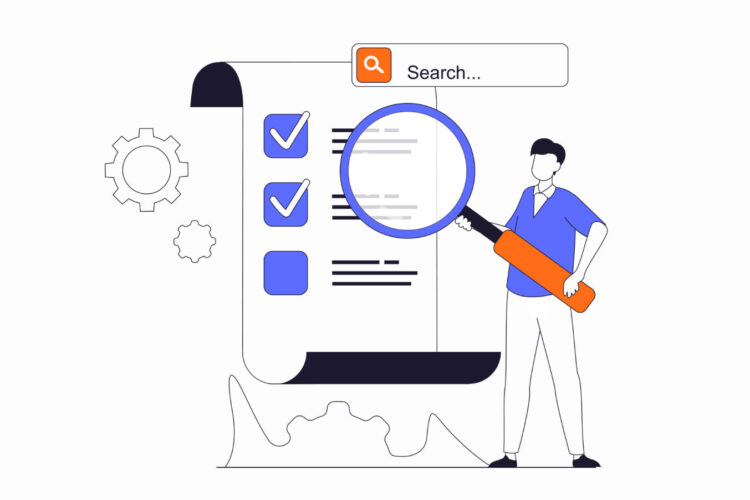
ETCマイレージは「制度は継続だが、路線ごとの運用が変わる」前提でチェック体制を作ると取りこぼしを防げます。
要は、公式サイトで方針を確認→路線別お知らせで自分の利用ルートの扱いを確認→会員マイページで実際の反映を確認、という三段構えです。
特に“発表日→適用開始日”の時差を見落とすと、ポイント付与の有無や自動還元の交換タイミングでズレが出ます。
月初は残高・期限・自動還元のON/OFFを点検、月中は走行実績と付与状況を突合し、月末は未交換分の掃除と還元額の消化ルートを確保、という定例運用にすると安定します。
家族・社用でカードが複数ある場合は、名義・カード・車両のひも付けを固定し、マイレージ対象路線の比率を月次で可視化するのが実務的です。
| 見る場所 | 確認内容 | 頻度・ポイント |
|---|---|---|
| ETCマイレージ公式 | 制度全体の方針・Q&A・重要なお知らせ | 月初/変更時。発表日と適用日を必ず控える |
| 路線別公式サイト | ポイント付与終了・還元可否・交換単位 | 新着時。自分の通行路線を重点的に |
| 会員マイページ | 保有ポイント・還元額・反映状況 | 月初・月末。自動還元ON/OFFと期限を確認 |
- 月初:残高・期限・自動還元設定を点検
- 月中:走行実績と付与・交換の突合
- 月末:端数は手動交換→翌月の消化ルートを先取り
公式サイト→路線別お知らせ→反映確認
“終了”情報は路線単位で出ることが多く、まずは公式の発表源を正しくたどることが重要です。
最初にETCマイレージ公式の「お知らせ」「Q&A」で制度全体の前提を確認し、次に自分が走る可能性の高い道路事業者(NEXCO各社/名古屋高速/神戸市道路公社など)のニュース欄で、ポイント付与終了や運用変更の告知をチェックします。
最後に会員マイページで「保有ポイント/還元額/事業者別履歴」を開き、実際に自分の勘定でどう反映されているかを確認します。
とくに“付与終了→還元額は利用可”の路線では、ポイントの交換期限と自動還元の到達状況がズレやすいので要注意です。
【確認ステップ】
- ETCマイレージ公式の最新情報を確認→制度全体の変更有無を把握
- 路線別公式のお知らせで〈付与終了/還元可否/適用日〉を確認
- 会員マイページで残高・履歴の反映と期限を点検(必要なら手動交換)
| チェック項目 | 見るべき数値・記載 | 見落としがちな点 |
|---|---|---|
| 適用日 | 告知の「いつから」 | 発表日と混同しない→当日以降の走行が対象 |
| 付与の有無 | ポイント付与あり/なし | 「還元のみ可」との区別(付与は終了でも還元は使える) |
| 交換単位 | 自動還元の交換条件 | 端数が残りやすい→手動交換の計画が必要 |
マイページ通知設定と月次モニタリング
最新情報の見落としを防ぐには、会員マイページの通知と自前のモニタリングを組み合わせます。通知メール(お知らせ・交換・期限関連)をONにし、迷惑メール振り分けを回避。
ダッシュボードでは、①保有ポイント(期限別の残高)、②自動還元の到達見込み、③還元額の残量と消化先路線、の3つを毎月同じ指標で追うと安定します。
年度末に近づくほど端数が出やすいため、月初の時点で“今月自動交換で到達しない分”を洗い出し、月中〜月末前に手動交換→翌月の消化ルートを決めておくと失効ゼロ運用が可能です。
社用の場合は、経費締めと同じサイクルで残高・期限のレポートを作成すると、部門間での運用ブレを抑えられます。
| 指標 | 見る理由 | アクション |
|---|---|---|
| 期限別残高 | 失効を未然に防ぐ | 期限が近い分→手動交換→消化ルート確保 |
| 自動還元到達見込み | 自動で交換できるか判断 | 到達しない月は端数を手動交換 |
| 還元額の残量 | 翌月の充当計画を立てる | 対象路線の通行予定を前倒しで組む |
- 通知ON+迷惑メール除外設定→見逃しゼロ
- 月初に3指標(期限・到達・残量)を固定フォーマットで確認
- 端数は月中に手動交換→月末の駆け込みを回避
家族・社用の運用ルール見直し3ポイント
家族や社内で複数カードを使うと、回数やポイントの分散が起こりやすく、付与終了路線の混在で管理が煩雑になります。
名義・カード・車両の対応関係を固定し、マイレージ対象路線での走行は極力1枚のカードに集約する方針に改めましょう。
名義の付替や会員間のポイント移動はできないため、カードの“貸し借り前提”をやめ、各自の会員で運用するのが原則です。
社用では、対象外路線の多用部門には「クレジットカード還元や独自割引を軸に、NEXCO区間で還元額を消化する」ポリシーを明文化し、締日前の残高確認と手動交換をルーチン化します。
【見直しポイント】
- 集約:対象路線の走行はできるだけ同一カードへ集約
- 分担:名義・カード・車両の固定化→貸し借りを禁止
- 締め:月末前の残高・期限確認→端数は手動交換で掃除
| ルール | 狙い | 運用の具体策 |
|---|---|---|
| カード集約 | 回数・付与の取りこぼし防止 | 対象路線の主運転者を決め、カードを一本化 |
| 役割分担 | 名義・車両の混線回避 | 車両ごとに会員・カードを固定し台帳で管理 |
| 月次締め | 失効ゼロ・還元消化の徹底 | 締日前に残高報告→端数手動交換→翌月の消化計画 |
- 会員間の譲渡・合算は不可→貸し借り運用はNG
- 対象外路線は“貯まらない”前提→別の還元策を明文化
- 新規車両・カード導入時は月初開始→集計をシンプルに
まとめ
ETCマイレージ自体は継続、終了は路線単位の“ポイント付与”が中心です。まずは公式サイトで路線別のお知らせを確認し、残ポイントは還元額へ交換→対象路線で計画的に消化。
マイページ通知と月次のモニタリングを習慣化すれば、取りこぼしを防ぎつつ、他の割引制度とも無理なく両立できます。