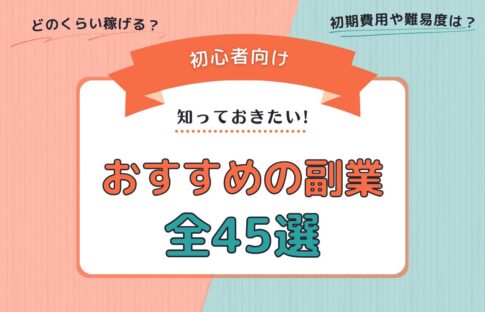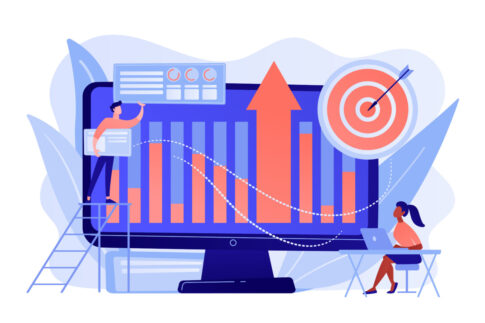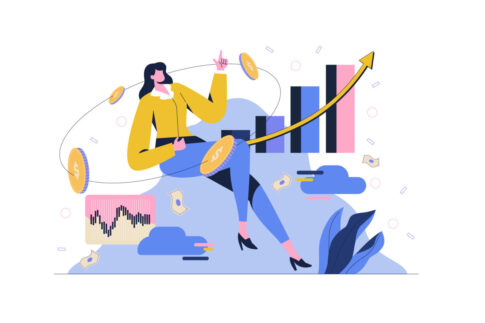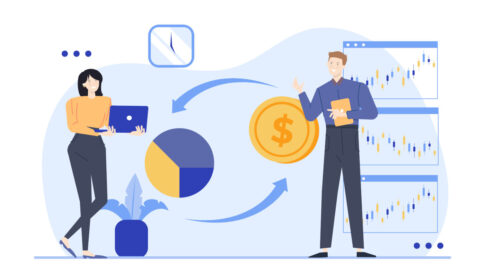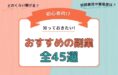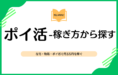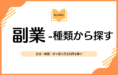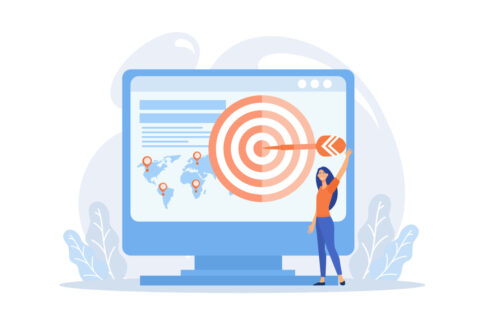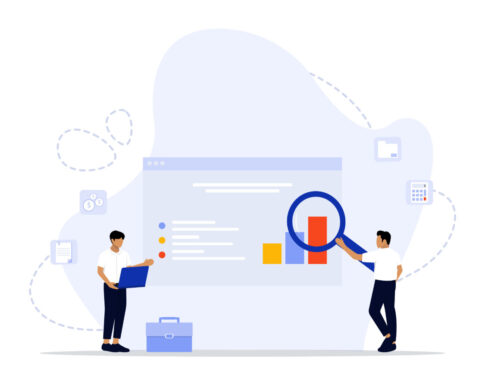この記事では、株式投資初心者がどんな本を選ぶべきかのポイントや、おすすめの10冊、副業につなげるための活用法などを解説していきます。
初心者でも無理なく投資知識を身につけられる方法や、失敗を最小限に抑えるリスク管理のコツもご紹介します。最新の投資トレンドを踏まえた情報も取り入れ、学びを深めるポイントを解説します。
目次
株式投資の本を活用するメリット

株式投資をこれから始める方にとって、本を活用するメリットは大きいです。インターネット上には数多くの情報があふれていますが、本は体系的にまとめられており、重要なポイントを網羅的に学習しやすいのが特徴です。
さらに、専門家や投資家が実体験をもとに執筆しているため、初心者がつまずきやすい点や失敗の回避策も具体的に理解できます。本を読むことで基礎知識をしっかり固めながら、成功例だけでなく失敗例にも触れられるので、独学にありがちな遠回りを避けやすくなります。
特に株式投資は日々のニュースや経済状況に左右される面があるため、知識のアップデートが欠かせません。本の中には、長期投資の視点や銘柄分析の手法など、投資スタイルに合わせた考え方を提案しているものも多く存在します。
こうした書籍を活用すれば、投資方針を確立する手助けとなり、自分に適したポートフォリオを作りやすくなります。
また、副業として株式投資を捉える際にも、本で学んだ知識がある程度体系立っていれば、時間や資金を効率的に使えるようになるでしょう。
最初から大きなリターンを狙うのではなく、小額から確実に知識と経験を積み重ねることで、投資の失敗リスクを下げることが可能です。しっかりと学びながら始めるためにも、株式投資関連の本は必ず目を通しておきたい情報源といえます。
投資初心者が基礎から学べる理由
株式投資を始める際には、証券口座の開設や銘柄選びなど、多くの壁が立ちはだかります。しかし、本を活用することで初心者が基礎から段階的に学ぶことができるのです。多くの株式投資の入門書は、チャートの読み方や売買のタイミング、配当金の仕組みなどを順を追って解説しています。
特に初心者がつまずきがちな専門用語についても、わかりやすい言葉で補足が入っているため、投資に関する苦手意識を減らすことができます。
また、本はネット記事と比較して情報が整理されているケースが多いので、「なぜこの知識が大切か」「どのように応用できるか」が体系的に理解しやすい点もメリットです。さらに、多くの書籍では実際に投資を成功させた経験談や、失敗体験から学んだノウハウが盛り込まれています。
こうした生の声を読みながら学習することで、初心者でもリアルな投資の流れや注意点を把握しやすくなります。単に用語を覚えるだけでなく、プロ投資家がどのように考え、どんな場面でリスクを回避しているのかを知るのは大きな学びです。以下のボックスでは、投資初心者が学習を効率化するステップをまとめてみました。
- Step1:入門書で基本用語と投資の流れを理解する
- Step2:実践的な体験談や事例が掲載された書籍を読む
- Step3:学んだ知識を少額投資で試し、感覚を掴む
- Step4:投資スタイルに合った書籍を探し、継続学習する
こうしたステップを踏むことで、初心者でも確実に投資知識を身につけながら実践に移せるようになります。
本を活用すれば、株式投資の全体像が頭に入りやすくなり、日々のニュースや株価の変動がどのように自分の投資に影響するのか、俯瞰的に見る力が養われます。その結果、投資のハードルを下げ、長期的に安定した成果を目指せるようになるでしょう。
リスク管理や心構えを身につけやすいポイント
株式投資では、相場の変動や企業業績の悪化など、さまざまなリスクと向き合わなければなりません。書籍の中には、過去の大暴落や失敗事例などを詳細に解説しているものが多く、それらを学ぶことでリスク管理に関する知識が身につきやすくなります。
リスク管理の具体的な例としては、資産を一つの銘柄に集中させず複数の銘柄や業種に分散投資する手法や、損失を最小限に抑えるための損切りルールの設計などが挙げられます。
また、投資における心構えとして、短期的な値動きに一喜一憂しすぎないメンタルの保ち方も重要です。心理的なブレを最小化するためには、あらかじめ自分が許容できる損失の範囲を決めておき、過度なレバレッジをかけないことが大切になります。下記のテーブルでは、代表的なリスクと対策の例を整理しました。
| リスク要素 | 対策 |
|---|---|
| 相場の急変 | 小口分散投資やドルコスト平均法を導入し、急激な価格変動に備える |
| 資金不足 | 生活費を優先的に確保し、余剰資金を投資に回すことで精神的負担を軽減 |
| 情報不足 | 書籍やセミナーで基礎を学び、企業のIR情報や市況ニュースを定期的にチェック |
| 過度な期待 | 投資目的を明確にし、長期的な視点を持つことで短期的な変動に流されない |
このように、書籍を通じてリスク要因を体系的に理解することで、日常的にリスクと向き合う意識を高めることができます。さらに、本は執筆者の経験談や他の投資家の実例を紹介している場合が多く、それらを参考にすることで「どこに落とし穴があるのか」を具体的にイメージしやすくなります。
心構えとしては、投資は常に利益だけでなく損失の可能性も伴うものであることを前提に行動するのが大切です。本を活用すれば、理論だけでなくメンタル面の考え方も学びやすくなり、適切なリスクコントロールが可能になります。
こうした習慣を身につけておくと、市場の変動が大きい局面でも落ち着いて判断できるようになるでしょう。結果的に、長期的な投資成果を高めるための基盤が築かれ、副業としての株式投資にもプラスに働くはずです。
初心者が知っておきたい本の選び方

初心者が株式投資の本を選ぶときに大切なのは、自分のレベルや目的に合った書籍を見極めることです。株式投資の世界にはさまざまな理論や手法が存在しますが、初心者の段階では高度な専門用語が多いものより、基礎知識を丁寧に解説しているものを選ぶのがおすすめです。
なぜなら、投資に必要な土台を築くためには、チャートの読み方や用語の意味を確実に理解することが欠かせないからです。また、初心者用の書籍ほど実際の売買例や具体的な数値が示されているケースが多く、学んだ内容をイメージしやすいというメリットがあります。
加えて、文章の分量や難易度も見逃せないポイントです。あまりにも専門的な内容ばかりが書かれている本では途中で挫折してしまう可能性が高いですし、逆に内容が薄すぎると満足な知識を得られません。
そのため、「なぜこの投資法が有効なのか」「どのようにリスクを管理するのか」など、投資家としての心構えや基本戦略がわかりやすく解説された本を選ぶと良いでしょう。
さらに、読みやすいレイアウトや図表の多さも重要です。文字だけでなくイラストや図表が活用されていると、複雑な理論も視覚的に捉えられるので理解が深まります。
とくに投資の初心者は利益を出すことばかりを意識しがちですが、まずは「継続的に学習する姿勢」を身につけることが大切です。その最初の入り口として、自分が読み進めやすく理解しやすい本を厳選してみてください。
こうした視点を押さえておくと、無数にある株式投資の書籍の中から自分にピッタリの一冊を見つけることができるはずです。時間やコストを有効に使いながら、しっかりと基礎を固めるためにも、最初の本選びは慎重に行うようにしましょう。
著者や出版社で選ぶコツ
株式投資の本を選ぶ際には、著者や出版社の特徴を見極めることも大切です。まず、著者の経歴や実績を確認してみましょう。株式投資の世界では、長年のトレーダー経験や証券アナリストとしての実績を持つ方が執筆している場合があります。
実務経験が豊富な著者の本は、失敗例や成功事例など具体的なエピソードが多く、リアルな投資イメージをつかみやすいです。特に初心者にとっては、経験に基づくアドバイスは教科書的な内容だけでは得られない学びをもたらします。
また、出版社によっても書籍の方向性や編集方針が異なるため、読みやすさや構成の仕方に違いがあります。大手出版社から出されている投資本は、正確な情報を信頼できるケースが多く、初心者が基礎を習得するにはうってつけです。
一方で、投資の専門出版社からリリースされている書籍は、独自の投資観や踏み込んだ分析が盛り込まれている場合があるため、より深い知識を身につけたい方には適しています。
ただし、初心者が最初から専門性の高い書籍に手を出すと、用語や理論に混乱してしまう可能性があるので注意が必要です。段階を踏んでレベルアップを図りたいときには、あえて著者の異なる複数の書籍を読むのも手段の一つです。読み比べをすることで、同じテーマでも解釈や伝え方に違いがあることを実感でき、より幅広い視野を得られます。
また、著者の出身業界や投資スタイル(短期売買、長期投資など)にも目を向けましょう。自分が目指す投資スタイルと一致する著者の本は、学んだ内容を実践しやすくなります。さらに、多くの書籍では「初心者向け」と銘打たれていても難易度にはばらつきがあります。
表紙やタイトルに惑わされず、目次やレビューをチェックすることで本の中身をある程度把握できるはずです。たとえば、目次に「PBRやPERなどの基礎指標の活用」「長期投資と短期トレードの違い」といった具体的な項目があるかどうか、初心者にも理解しやすい構成になっているかを見極めると失敗が少なくなります。
- 実務経験豊富な著者のリアルな経験談を学べる
- 出版社ごとの編集方針で読みやすさに違いがある
- 投資スタイルが著者と合えば知識を活かしやすい
- 複数の本を読み比べると多角的な視点が身につく
上記のように、著者や出版社の見極め方次第で、投資学習の効率やモチベーションが大きく変わります。特に副業として株式投資を検討している場合、限られた時間の中で効率的に情報を吸収したいはずです。
そのためには、まず書店やオンラインストアのレビューだけに頼るのではなく、著者の略歴や過去に執筆した書籍の評価などを調べてみるとよいでしょう。
そうすることで、「この人の考え方は自分にフィットしそうだ」と判断しやすくなります。やみくもに多数の本を買い込むよりも、厳選した数冊から確実に学ぶほうが、初心者にはスムーズな道のりです。
著者や出版社ごとの特徴を把握し、自分に合ったスタイルの本を選ぶことで、投資への理解が格段に深まり、自信を持って次のステップに進めるようになるでしょう。
最新情報が充実した書籍の見極め方
株式投資では、常に動いている相場や経済状況に対応するために、最新情報をしっかり追うことが大切です。そのため、書籍選びの際には「いつ出版されたか」「どの程度新しい情報が盛り込まれているか」を注目してみましょう。出版年が古すぎる書籍だと、市場環境や制度の変化に対応できていない場合があります。
たとえば、NISA(少額投資非課税制度)の拡充やスマホ証券の登場など、投資を取り巻く環境は数年単位で大きく変化しています。こういった新しい仕組みを理解せずに投資を始めてしまうと、思わぬタイミングを逃したり損をしたりするかもしれません。
逆に比較的最近の書籍であれば、最新制度に触れた解説や、インターネット取引の方法、さらにはAIを活用した投資手法などが取り上げられているケースも多いです。ただし、新しさだけを基準に選ぶのは危険です。
なぜなら、本が出版されるまでの編集プロセスに時間がかかることもあり、発刊時点で最新だった情報が数年後にはすでに古い内容となっている場合もあるからです。
そこで、「基本的な投資理論+最新の話題や制度をフォローしている本」を選ぶのがおすすめです。理論的な内容は大きく変わらなくても、最新のトピックや市場のトレンドを補足してくれる書籍なら、効率よく学習できるでしょう。
| チェック項目 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 出版年 | 直近2~3年以内の出版かを確認する。特に新制度やトレンドに追随しているか要チェック |
| 改訂版の有無 | 人気のある書籍は定期的に改訂版が発行されるため、可能なら最新改訂版を選ぶ |
| 著者の情報更新 | 著者がブログやSNSを通じて随時アップデートしている場合は、最新情報の反映度が高い可能性あり |
| 電子書籍対応 | 電子書籍は改訂が入りやすく、データを更新しやすいため最新情報を反映しやすい |
上記のような観点で本を選べば、必要なタイミングで最新知識を取り込みやすくなります。また、副業として株式投資に取り組む場合は、働きながら学習することになるため、更新された情報をすぐにチェックできるメリットは大きいです。
先ほど触れたように、出版年だけでなく改訂版の有無や著者の情報発信状況にも目を向けると、古いデータや時代遅れの手法を参照するリスクが低減できます。特に投資サービスや証券口座は日進月歩で進化しているので、書籍に掲載されているサービスが既に廃止されていたり、新しい手数料形態が導入されている可能性もあります。
その点を補うために、書籍と並行してインターネットで最新動向を調べるのもおすすめです。重要なのは、実践に移す時点で役立つ知識を持っているかどうかです。たとえば、スマホだけで株の売買が可能になった今の時代に、パソコン前提の投資手法ばかりが載っていると、初心者には実感が湧きにくいでしょう。
最新の市場動向を反映した書籍を選べば、現代的な投資スタイルにもスムーズに対応しやすくなります。こうした「現時点で使える情報」を得るために、本の出版年や改訂頻度、さらに著者の情報更新の頻度などをチェックしておくと安心です。
最新情報を常にキャッチアップできるようにしておけば、相場の変化にも柔軟に対応でき、長期的な資産形成をより着実に進めることができます。
株式投資の本の探し方

株式投資は、初心者でも比較的取り組みやすい副業の一つとして注目を集めています。実際に、少額から始められる点や、時間や場所を選ばずに取引できる利点があるため、会社員や主婦の方など、多忙な方でも比較的スムーズに参入できるのが魅力です。
とはいえ、株式投資は適切な知識とリスク管理が求められる世界でもあります。そのため、まずは信頼できる書籍を通じて基礎を固めることが成功への近道です。
特に、これから株式投資を始める方や、副業として投資の幅を広げたいと考えている方にとっては、入門書や実践書の選択が重要になります。具体的なケーススタディや著名な投資家の経験談が盛り込まれた本を選べば、難しいと感じる専門用語も身近に感じやすくなるでしょう。
また、書籍で得た知識を実践に移すことで、試行錯誤の過程を通じて自分の投資スタイルを確立しやすくなります。そこで今回は、副業にも役立つ株式投資のおすすめ本を10冊ピックアップしました。
長期投資の基本を学ぶものや、トレンドの読み方を身につけるものなど、多彩な書籍を取り上げていますので、自分の投資方針や生活リズムに合わせて、まずは一冊手に取ってみてください。
実際に読んで学んだ知識をもとに、少額から試してみることで、リスクを抑えながら収益を狙うための第一歩を踏み出しやすくなるはずです。
初心者向けの名著からベストセラーまで
株式投資の世界では、多くの名著やベストセラーが存在しますが、それぞれの書籍が取り扱うテーマや難易度、著者の経歴などは大きく異なります。初心者がまず注目したいのは、投資の基礎をしっかり学べることや、専門用語が丁寧に解説されているかどうかです。
投資の土台が固まっていない状態で、いきなり高度なテクニカル分析やデリバティブを扱う本を読んでも、なかなか内容が頭に入りづらいものです。逆に、初心者向けの入門書やベストセラーは、多くの読者から支持を受けているため、「なぜこの方法が有効なのか」をわかりやすい文体で説いているケースが多いのが特徴です。
さらに、投資の基本であるリスクヘッジや分散投資の考え方について、具体的な数字やエピソードを用いて解説している本も多いため、実際の取引場面をイメージしながら学習ができます。
- 基礎的な投資用語が整理されている書籍を選ぶ
- 成功・失敗事例が具体的に書かれている本を活用する
- ベストセラーは多くの人に読まれており、わかりやすさに定評がある
具体例としては、初心者向けに基本用語や売買手順を解説している書籍や、著名投資家の思想をわかりやすくかみ砕いて説明しているものが挙げられます。たとえば、長期投資のメリットや複利効果を事例を交えて説いた名著を読むと、自分がどのようなスタンスで投資に臨むべきか見えてきますし、今後の副業戦略も立てやすくなるはずです。
また、投資を続けるうえではモチベーション維持も重要になります。成功者の体験談が盛り込まれたベストセラーは、「こんなふうに実践すれば、自分も同じように成長できるかもしれない」というワクワク感を与えてくれます。
もちろん、株式投資に王道の成功法があるわけではなく、自分自身で試行錯誤を重ねながら経験値を積み上げることが大切ですが、良書を活用して基本を学ぶことで、大きな遠回りを避けることができるのです。
こうした入門からベストセラーに至るさまざまな書籍を読み比べてみると、同じテーマでも著者によってアプローチや解釈が異なることに気づくでしょう。それらを踏まえ、自分のライフスタイルや投資目的に合わせて柔軟に取り入れることで、副業としての株式投資をより充実させることが可能になります。
電子書籍や音声版を活用するメリット
最近では、紙の本だけでなく、電子書籍やオーディオブックといったデジタル媒体で株式投資の書籍を読む方も増えています。これらの形式を活用するメリットは主に3つあります。
まず一つ目は、いつでもどこでも学習できる点です。スマホやタブレットがあれば電車の中や休憩時間など、スキマ時間を有効活用して投資の勉強ができるため、副業として投資に取り組む方にとって非常に便利です。二つ目は、書籍の更新や改訂が入りやすい点です。
特に電子書籍は、紙の本に比べて改訂スピードが速いケースがあり、最新の制度やトレンドをフォローしやすくなっています。
三つ目は、紙の本と違って保管場所を取らないことです。多くの本を一気に持ち運べるため、「あのとき読んだ本の内容をもう一度確認したい」というときにも素早くアクセスできます。
| 媒体 | 特徴・メリット |
|---|---|
| 電子書籍 | スマホやタブレットで気軽に学習が可能。検索機能を活用すれば、目当てのキーワードをすぐに調べられる |
| 音声版 | 通勤や運動中でも耳で学習できるため、時間のない方やマルチタスクをしたい方におすすめ |
ただし、電子書籍や音声版がすべての投資家に向いているわけではありません。紙の本のほうが集中して学習しやすいと感じる方もいるでしょう。また、図解やチャートが多用されている書籍では、紙のほうが見やすいという意見もあります。
そこで、状況に応じて使い分けることが重要です。例えば、日々のスキマ時間には音声版で投資の概念をインプットし、じっくり考えたいときは紙の本や電子書籍で図表を確認するなど、複数のメディアを組み合わせることで効率を高めることができます。
とくに副業として投資を行う場合は、限られた時間を最大限に活用する必要があります。音声版なら通勤時間に学習し、電子書籍なら隙間時間で掴んだ知識を復習するというように、ライフスタイルに合わせた勉強スタイルを確立できるのがメリットです。
最終的に紙・電子・音声のどれをメインとするかは個人の好みによりますが、それぞれの媒体を組み合わせることで効率的かつ柔軟に学びを深められるのは間違いありません。
副業として株式投資を検討している方は、こうした学習ツールの特徴をしっかり把握し、自分に合った方法で知識をアップデートしていくことが、安定した投資成果を得るための鍵になります。
株式投資の本で得た知識を実践に活かすコツ

株式投資の本を読むと、理論や用語を学ぶだけでなく、実際の売買シミュレーションや成功事例など、具体的な活用法を知ることができます。しかし、知識を得ただけで終わらせてしまうと、本来の投資成果に結びつきにくいです。
そのため、本を読んで理解したポイントをすぐに実践へ落とし込む工夫が欠かせません。たとえば、まずは少額の資金を使い、書籍で学んだテクニカル指標や売買タイミングを試してみるのがおすすめです。
デモ口座を活用できる証券会社もあるため、リアルマネーの取引に抵抗がある場合は仮想取引で感覚をつかむとよいでしょう。こうしたステップを踏むことで、頭で理解したつもりになっていた考え方や手法が、実際の相場ではどのように機能するかが明確になります。
また、副業として株式投資を行う場合は、限られた時間の中で効率よく成果を上げる必要がありますので、読むだけではなく試行錯誤を繰り返すプロセスが重要です。
小さな額でも実際に取引を重ねることで、リスク管理の視点や損切りルールの設定など、机上の学習だけでは得られない実戦的な感覚が身につきます。
特に銘柄選びや投資スタイルの確立は、一度に覚えようとするのではなく、本で学んだ原則を自分なりにカスタマイズしながら継続的に検証していくことがポイントです。こうした実践を通じて「本から得た知識」をより深く腑に落とし、自分の資産形成に活かせるようになるでしょう。
学習内容をすぐにアウトプットする方法
株式投資の本を読んだら、その内容をできるだけ早くアウトプットしてみることをおすすめします。アウトプットの方法は人によってさまざまですが、読んだ内容をメモにまとめる、ブログやSNSで発信する、実際の取引で試してみるなど、行動に移すことが大切です。
特に初心者の方は読んだ直後に「どのような指標が役に立ちそうか」「どんなリスク対策が必要か」など、自分が学び取ったポイントを目に見える形にして整理すると理解が深まります。
たとえば、チャート分析の方法を学んだなら、気になる銘柄のチャートをスクリーンショットしておき、過去の値動きと学んだ分析方法を照らし合わせるといった具体的なアウトプットを実践してみるとよいでしょう。
さらに、家族や友人に自分の学習内容を説明してみる方法も効果的です。誰かにわかりやすく話そうとすると、知識がまだ曖昧な部分を再確認できるため、自然と理解度が高まります。
- 読書後すぐにメモやノートに要点を書き出す
- 実際の銘柄やチャートを活用して学びを実践的に検証する
- SNSやブログで内容を発信し、フィードバックをもらう
アウトプットの継続を習慣化すると、学んだ知識が自分の投資スタイルに落とし込みやすくなります。たとえば、朝の通勤時間に株式関連のニュースをチェックしながら「このニュースがどの銘柄に影響しそうか」「学んだ指標の視点で見るとどう評価できるか」などを考えると、自然とインプットとアウトプットが循環していきます。
最初は難しく感じるかもしれませんが、投資に対する理解が深まるほど、どのように相場を見ればいいかが少しずつ見えてくるはずです。
限られた時間の中でも、ちょっとした工夫を凝らすだけで学んだ知識を定着させる機会は作れますので、副業として投資を行う方も積極的に取り組んでみてください。
学習と実践を結びつけるアクションを繰り返すうちに、知識と経験の両面を強化でき、より確かな投資判断を下せるようになるでしょう。
継続的に成長を目指すためのロードマップ
株式投資は、一度学べば終わりというものではなく、継続的な学習と実践を重ねていくことでスキルが磨かれていきます。そこでおすすめなのが、自分なりのロードマップを作成することです。
まずは短期的な目標として「毎月1冊は投資関連の本を読む」「週に1回は相場をチェックして投資日誌を付ける」など、実行可能なタスクを設定してみてください。
その次に、中期的な目標として「自分の投資スタイルを確立し、リスク管理や損切りルールを明確にする」などを掲げるとよいでしょう。
さらに長期的には「副業収入として投資利益の割合を○%以上にする」「将来的に配当金や売買益を資産形成の柱に加える」といったビジョンを持つことも大切です。ロードマップを活用するメリットは、行き当たりばったりで投資を続けるのではなく、段階的に成長を実感しながら取り組める点にあります。
| 期間 | 主なタスク・目標 |
|---|---|
| 短期(1~3ヶ月) | 投資本を活用して基礎知識を固める。少額投資やデモ取引で実践に慣れる。投資日誌を付けて振り返りを行う |
| 中期(6ヶ月~1年) | 投資スタイルの確立。リスク管理や損切りルールを定め、ポートフォリオの分散を試みる。新制度や経済ニュースを定期的にキャッチアップする |
| 長期(1年以上) | 副業としての投資収益の向上。余裕資金を拡充し、長期投資や配当金再投資などで資産形成を進める |
こうしたロードマップを参考にしながら、定期的に目標を見直していくことも重要です。たとえば、思うように利益を出せなかったり、相場の変動で精神的に大きなストレスを感じたりする場面が出てくるかもしれません。
その際には、投資本で得た知識や失敗事例を再確認し、ルールを調整してみるといった柔軟な対応が求められます。
最初から完璧を求めるのではなく、学習と実践を繰り返して少しずつ改善を重ねていく姿勢が、長期的な成長につながるのです。副業として投資を行う方にとっては、特に時間の使い方がカギとなりますが、ロードマップを作っておけば、隙間時間での学習や売買判断の優先度を明確にしやすくなります。
こうした習慣を継続的に積み上げることで、やがて自分なりの投資哲学が確立され、株式投資による収益を副業や将来の資産形成の柱に据える道も開けてくるでしょう。
まとめ
この記事でご紹介した株式投資の本を活用すれば、初心者でも基本を理解しながらステップアップが可能です。自分に合った書籍を選び、学んだ知識を実践に繋げることで、副業としての成果や長期的な資産形成に役立てられます。
各書籍の特徴を把握して効率よく学習を進めてみてください。投資を継続する中で得られる経験や判断力は、人生を豊かにする大きな武器になります。