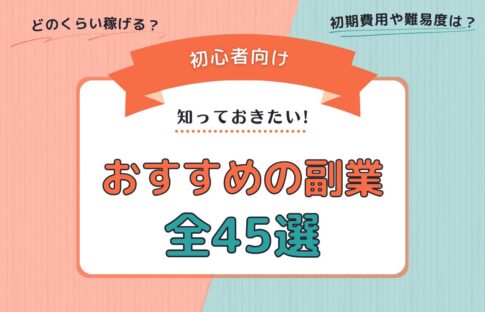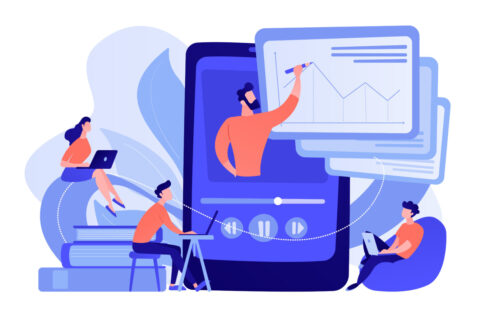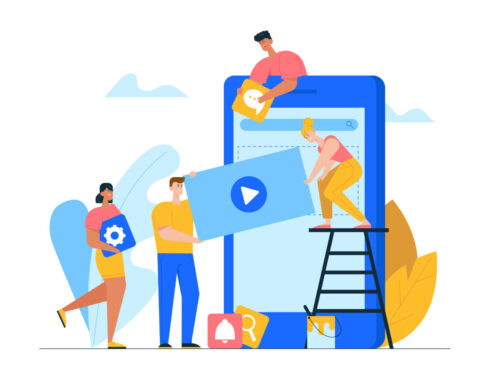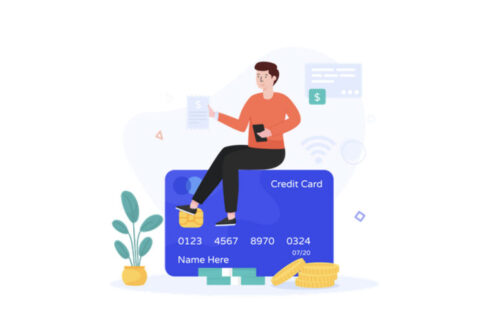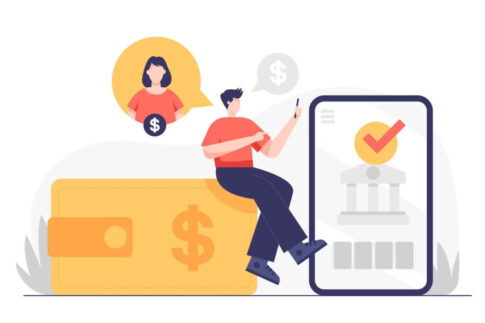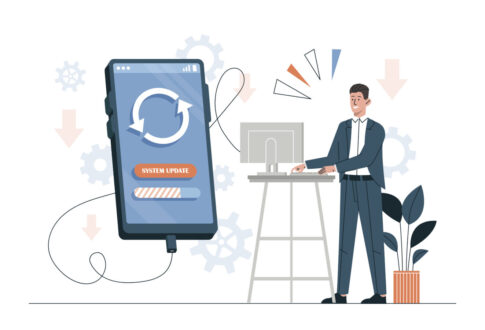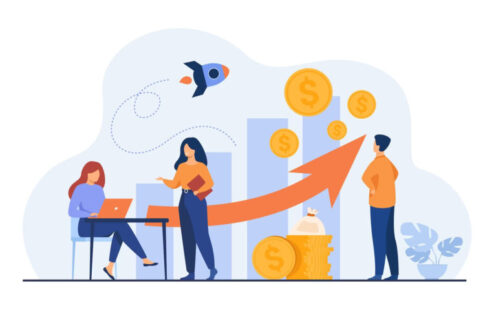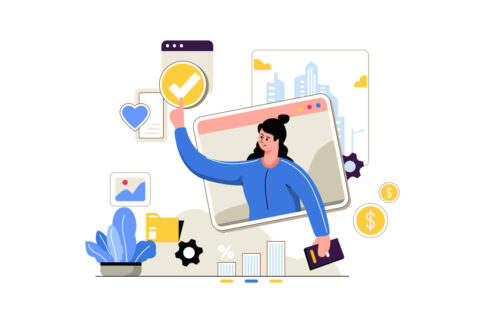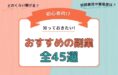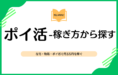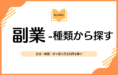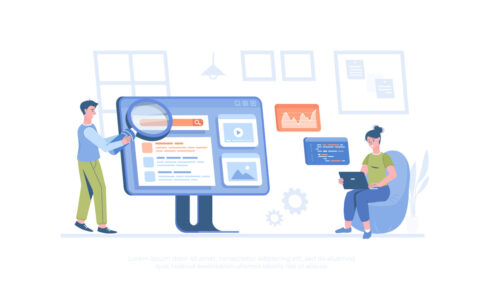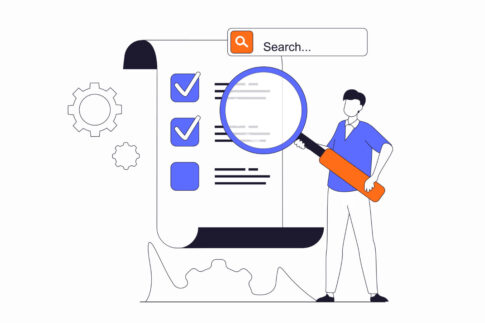TOKYUルートが廃止され、「もうANAマイルをお得に貯める方法がない」と嘆いている陸マイラーの方も多いのではないでしょうか。実は、還元率70%を維持しながら全国どこでも利用できる「みずほルート」が存在します。
Vポイント(旧Tポイント)やGポイントを経由し、JQ CARDセゾンやみずほマイレージクラブカードを活用するだけで、ウェブ上で簡単にANAマイルへ交換可能です。TOKYUルートの75%からはやや下がるものの、十分に高還元を狙えるため、今後の陸マイラー活動にぜひ取り入れてみてください。
目次
TOKYUルート廃止!みずほルートのメリット

TOKYUルートの廃止は、多くの陸マイラーにとって大きな衝撃だったと思います。これまで75%という高い還元率でポイントサイトのポイントをANAマイルに交換できたため、効率よくマイルを貯められる王道ルートとして非常に人気がありました。
しかし2025年現在、そのTOKYUルートが使えなくなったことで「陸マイラー活動はもう難しいのでは?」と感じた方もいるのではないでしょうか。そこで注目されているのが「みずほルート」です。みずほルートは還元率70%という好条件を実現しており、TOKYUルート廃止後の代替として大きく期待されています。
まず、みずほルートの大きなメリットは日本全国どこに住んでいても活用しやすいことです。TOKYUルートの場合、一部の地域やサービス利用が限定的であったり、nimocaルートのように交換機が設置されている地域が限られているケースもありました。
一方、みずほルートはウェブ上でポイント交換が完結するため、地理的な制約をほぼ受けません。たとえばnimocaルートは九州や函館にある交換機に足を運ぶ必要があり、遠方の人にとっては手間とコストがかかりすぎるのが難点でした。そうしたハードルがみずほルートには存在しないのです。
また、みずほルートを使うには「JQ CARD セゾン」と「みずほマイレージクラブカード/ANA」が必要になりますが、これらは年会費無料(または条件付き無料)のカードなので、TOKYUルート時代のような大きな固定費負担はありません。
JQ CARD セゾンは年1回以上の利用で翌年度の年会費が無料になりますし、みずほマイレージクラブカード/ANAはそもそも年会費がかからないため、陸マイラー活動のコストを極力抑えられます。ウェブ上ですべて完結する流れも含めて、TOKYUルートほどの簡単さや75%という高還元には及ばないものの、全国対応かつ70%という高水準を維持できる点は非常に魅力的といえるでしょう。
みずほルートを活用する場合、ポイントサイトで得たポイントをVポイント(旧Tポイント)やGポイントに交換し、そこからJRキューポ→永久不滅ポイント→ANAマイルというステップを踏む必要があります。交換回数が多く感じるかもしれませんが、その分しっかり70%還元が可能になります。
TOKYUルート廃止後、新しい交換ルートを模索している陸マイラーにとっては、他に nimocaルートや ソラチカルート(廃止済み)など検討すべき選択肢はありましたが、nimocaルートは地理的制限が大きく、ソラチカルートはすでに使えないため、みずほルートが一番バランスに優れているのです。
特に、みずほ銀行口座を持っていればウェブ上で簡単に設定が行える仕組みが用意されており、多少の手間はあれどTOKYUルート時代のように大きな障壁はありません。
- 全国対応で交換機などの地域制限がない
- JQ CARD セゾン・みずほマイレージクラブカードの年会費が条件付き無料
- 還元率70%をキープしながらウェブ上で完結できる
まとめると、TOKYUルート廃止で一時的に混乱が生じた陸マイラー界隈ですが、みずほルートという形で十分に高い還元率(70%)を確保しつつ、全国どこからでも利用しやすいルートが確立しています。地域を問わず、自宅にいながらウェブでポイント交換が完結するため、nimocaルートのように遠距離移動をする手間もかからないのが嬉しいポイントです。
無論、交換ルートが少し長くなり、複数回の交換手順があるのは事実ですが、TOKYUルートが廃止された今の陸マイラー事情では「代替ルート」としては最も実用的な選択肢でしょう。続いて、TOKYUルートが廃止に至った背景やみずほルートの具体的な仕組みなどを詳しく見ていきます。
75%→70%に変わった背景とみずほルートの仕組み
TOKYUルートが廃止され、陸マイラーにとっての還元率が75%から70%へと下がってしまった背景には、航空会社やポイントサイト側の制度変更や提携関係の見直しが挙げられます。2022年3月の廃止以降、それまで簡単で高還元だったTOKYUルートに頼っていた人は軒並み別のルートを探す必要に迫られました。
ANAマイルを貯めるうえではnimocaルートやみずほルートが代替案として浮上し、一部の地理的条件をクリアできる人はnimocaルート(還元率70%)を使いましたが、北海道や九州に行かなければならないなど大きなハードルがあるのがネック。そこで注目されたのが、どこに住んでいてもウェブ上で完結し、やはり70%という高還元を維持できるみずほルートなのです。
みずほルートの具体的な仕組みは、以下のステップで進行します。まず、ポイントサイトで貯めたポイントをVポイント(旧Tポイント)またはGポイントに交換します。次にJRキューポに交換し、JRキューポから永久不滅ポイント(JQ CARD セゾンが必須)に変換。
最後に、永久不滅ポイントをANAマイル(みずほマイレージクラブカード/ANAが必須)へ移行するという流れです。いくつかのカード発行とポイント交換を経るため、一見ややこしく見えますが、TOKYUルート時代と違って全国どこからでも手続きできるという利点が大きく、結果的に70%の還元率を達成できます。
下記の表でみずほルートの大まかなフローをまとめました。
| 手順 | 変換先 |
|---|---|
| 1 | ポイントサイト → Vポイント(旧Tポイント) or Gポイント |
| 2 | Vポイント / Gポイント → JRキューポ |
| 3 | JRキューポ → 永久不滅ポイント(JQ CARD セゾン必須) |
| 4 | 永久不滅ポイント → ANAマイル(みずほマイレージクラブカード/ANA必須) |
複数の交換を経るため所要日数や手間は否めませんが、それでもTOKYUルート廃止後ではANAマイルへの還元率70%という高水準を維持できる数少ないルートなのです。
しかも、nimocaルートと違って特定の地域に行く必要がなく、カード申し込みやウェブ手続きを行うだけでANAマイルへ交換できるのは大きな強み。各段階で交換手数料や交換レートをチェックしておけば、想定外に還元率が下がる心配も少なく安心して運用できます。
ただし、みずほルートを使うには「JQ CARD セゾン」と「みずほマイレージクラブカード/ANA」の2種類のクレジットカードが必要になります。年会費の設定はあるものの、JQ CARD セゾンは年1回以上の利用で翌年の年会費が無料になり、みずほマイレージクラブカード/ANAは年会費がかからないため、実質的な維持費はほぼゼロに近い形を実現できます。
このように、TOKYUルートが廃止された経緯を踏まえると、みずほルートの誕生は陸マイラーにとって非常にありがたい選択肢といえるでしょう。続いてはnimocaルートなど他の交換ルートとの比較を通じて、みずほルートの優位性をさらに具体的に検証していきます。
nimocaルートなど他ルートとの比較で見える優位性
TOKYUルートの廃止後、ANAマイルを高還元率で交換できるルートとしては「nimocaルート」と「みずほルート」の2種類が特に注目されるようになりました。どちらも70%の還元率でANAマイルへ変換できるため、一見するとほぼ同じように見えるかもしれません。
しかし、地域的な制約や手続きの手間などを考慮すると、多くの人にとってみずほルートのほうが使いやすいケースが多いと言えます。以下では、nimocaルートとみずほルートの主な違いを比較してみましょう。
- nimocaルートは九州・函館など特定の地域にある交換機での手続きが必要
- みずほルートはWeb上で完結し、全国どこからでも対応可能
- 両者ともANAマイルへの還元率は70%だが、手続きやカード発行の有無が異なる
nimocaルートを利用する場合、九州や函館にある交換機を実際に訪れ、ポイントをnimocaポイントに変換してからANAマイルへ交換する流れが必要です。地元に住んでいる人や旅行で頻繁にその地域を訪れる人にとっては、そこまで大きな障壁ではないかもしれません。
しかし、遠方に住んでいる陸マイラーにとってわざわざ現地まで行って交換作業を行うのは現実的ではなく、実質的に利用が難しいと感じるでしょう。一方、みずほルートであればカード発行こそ必要なものの、すべての交換ステップをWeb上で完結できるため、地理的な制限を気にすることなく誰でも70%還元を享受できます。
また、nimocaルートの場合はnimocaポイントやPexポイントなどの手続きが多く、交換機での操作ミスによるトラブルや交換時間のロスが発生するリスクも存在します。
みずほルートにおいては、ポイントサイトで獲得したポイントをVポイント(旧Tポイント)またはGポイントに交換し、JRキューポ→永久不滅ポイント→ANAマイルという流れを踏むため、多少のステップはあれどWeb完結の気軽さが優位と言えるでしょう。特に忙しい会社員や学生、家族がいる陸マイラーにとって、物理的な移動が不要なのは大きなメリットです。
ただし、nimocaルートが絶対に劣っているというわけではありません。九州や函館に住んでいる方や、たまたま旅行などの理由で現地に行く予定がある人なら、nimocaルートでも同じ70%の還元率を狙えるため問題ありません。
実際に交換機のある施設が近くにあるなら、手続き自体は数分で済むので慣れればスムーズです。とはいえ、多くの陸マイラーは地理的なハードルを考慮してみずほルートを選ぶ傾向が強いのが現状です。
結論として、TOKYUルート廃止後にANAマイルを70%の高還元率で交換したい場合、nimocaルートが利用できる地域の人ならそのままnimocaルートを使う選択も十分にアリです。しかし、地域的な制約なしで誰でも実践しやすいのはみずほルートのほうであり、特にWeb上だけで完結できる手軽さとカード年会費が実質無料に抑えられる点が大きく評価されています。
次の見出しでは、みずほルートの具体的な利用手順と必要なクレジットカードについて詳しく解説し、還元率70%を維持するための注意点をまとめます。
みずほルートの手順と必要なカード

みずほルートは、TOKYUルート廃止後に還元率70%でANAマイルへ交換できる貴重なルートとして、陸マイラーから注目を集めています。このルートを利用するには、ポイントサイトで貯めたポイントをVポイント(旧Tポイント)かGポイントへ変換し、その後JRキューポ→永久不滅ポイント→ANAマイルという手順を踏むのが特徴です。
一見すると交換回数が多く複雑そうですが、実際はすべてウェブ上で手続きを完結できるため、日本全国どこに住んでいても利用しやすい点がメリットです。また、交換時に必要になるクレジットカードは「JQ CARDセゾン」と「みずほマイレージクラブカード/ANA」の2枚ですが、年会費が実質無料または条件付き無料となっており、大きなコストをかけずに導入できるのも強みといえます。
特に、JQ CARDセゾンはJRキューポへの交換で必須になるカードであり、年1回以上の利用で翌年度の年会費が無料になるため、陸マイラー活動を続けるうえでの固定費負担を抑えられます。一方のみずほマイレージクラブカード/ANAは年会費がかからず、ANAマイルへの移行時に必要となります。
この2枚をそろえておけば、TOKYUルートのように物理的な交換機などを使わずにポイントをウェブ上だけでANAマイルへ変換できるのが大きなメリットです。
nimocaルートと同じ還元率70%を達成しつつも、地理的制約がほとんどないため、多くの陸マイラーにとって利用しやすいルートといえます。還元率がTOKYUルートの75%よりは下がったとはいえ、70%を維持できるルートは貴重であり、TOKYUルート廃止後の代替策として積極的に活用する価値が十分にあるでしょう。
次の見出しでは、このみずほルートを使ってANAマイルへ交換する具体的なステップを整理し、それぞれの段階で押さえておきたいポイントを詳しく解説します。
ANAマイルへ交換する具体的ステップ
みずほルートを通じてANAマイルへ変換するには、いくつかのステップを踏む必要があります。ポイントサイトからANAマイルに至るまでの交換ルートが複数回に分かれるため、慣れないうちは面倒に感じるかもしれません。
しかし、それを乗り越えれば還元率70%を実現できるため、TOKYUルートが廃止された現状では非常に有力な方法といえます。以下では、具体的な流れを順を追って見ていきましょう。
- ポイントサイトでポイントを貯める
普段から使っているポイントサイト(ハピタスやモッピー、ECナビなど)で案件をこなし、ポイントを獲得します。重要なのは、みずほルートに対応するかたちでVポイント(旧Tポイント)やGポイントへの交換が可能かどうかを事前に確認しておくことです。 - Vポイント(旧Tポイント)またはGポイントへ交換
ポイントサイトから直接Vポイントへ交換できる場合はそのルートを、できない場合はポイント交換サイト(ドットマネーやPeXなど)を経由してVポイントへ変換します。また、Gポイントでも同様にJRキューポへの移行が可能なので、どちらを使うかはポイントサイトの交換ルールや自身の環境に合わせて選ぶと良いでしょう。 - JRキューポへ移行
VポイントやGポイントをJRキューポに変換します。ここでJQ CARDセゾンが必須になります。JQ CARDセゾンがあることで、JRキューポ→永久不滅ポイントという変換が可能になるのです。 - 永久不滅ポイントへ交換
JRキューポから永久不滅ポイントに移行します。まだANAマイルには達しませんが、次のステップでみずほマイレージクラブカード/ANAが必要になります。 - ANAマイルへの最終変換
永久不滅ポイントをANAマイルに交換する際、みずほマイレージクラブカード/ANAが必要です。ここでしっかりカードを紐づけておけば、ポイントが70%の還元率でANAマイルに姿を変えます。
- ポイントサイト → Vポイント(or Gポイント)
- Vポイント(or Gポイント) → JRキューポ(JQ CARDセゾン)
- JRキューポ → 永久不滅ポイント
- 永久不滅ポイント → ANAマイル(みずほマイレージクラブカード/ANA)
このように、合計4回の交換を経ることで70%の還元率が得られます。TOKYUルート時代と比べるとステップが多いと感じるかもしれませんが、すべてウェブ上で完結するため、地理的な制約を受けずに交換を進められるのが強みです。
注意点としては、各交換の際にレートや手数料が変わらないか、タイミングによって一部キャンペーンが行われないかなどを都度チェックする必要があります。こうした細かい部分を把握しておくと、想定外に還元率が下がるトラブルを防ぎやすいでしょう。
JQ CARDセゾン&みずほマイレージクラブカードの注意点
みずほルートを利用するには「JQ CARDセゾン」と「みずほマイレージクラブカード/ANA」という2枚のカードが欠かせません。
いずれも年会費が実質無料(または条件付き無料)となっており、陸マイラーが持ちやすい仕組みになっています。ただし、いくつか注意しておきたい点が存在するため、発行前に以下の事項をチェックしておくとトラブルを避けられます。
まず、JQ CARDセゾンは年会費1,375円(税込)が必要ですが、年1回以上のカード利用があれば翌年の年会費が無料になる特典があります。つまり、陸マイラーのメインカードとして積極的に利用するならば実質的に年会費をゼロにできるわけです。
しかし、全く使わないままだと年会費が発生することになるので、最低でも1回は意識して利用しましょう。JQ CARDセゾンがなければJRキューポ→永久不滅ポイントのルートが成立しないため、陸マイラーにとって必須のカードといえます。
一方、みずほマイレージクラブカード/ANAは年会費無料で維持できるものの、ANAマイル移行時に手続きをスムーズに行うための確認がいくつか必要です。特に、カード発行時にANAマイレージクラブとの連携が完了していないと、ポイント→ANAマイルへの変換が滞るケースがあります。
発行後にみずほ銀行のオンラインサービスやアプリを使って設定する流れが案内されるため、初期登録の段階でしっかり手順を踏んでおけば問題ありません。とはいえ、手数料などは発生しないため、コスト面では維持しやすいカードとなっています。
- JQ CARDセゾンは年1回以上の利用で翌年の年会費無料だが、一切使わないままだと年会費が発生
- みずほマイレージクラブカード/ANAは年会費無料だが、ANAマイレージクラブの連携設定を忘れない
- カード発行時期によっては入会キャンペーンがあるため、タイミングを見計らうと特典を獲得しやすい
また、カードを発行するタイミングによってはキャンペーンやボーナスポイントが付与される場合があります。特にJQ CARDセゾンやみずほ銀行関連のキャンペーンは、期間限定でポイントを追加で獲得できる企画を展開することがあるので、そうしたタイミングを狙って発行すると最初からお得にスタートを切れます。
もちろん、カード発行には審査もあるため、まとめて大量のクレジットカードを同時に申し込むと審査落ちのリスクが高まるという点にも注意が必要です。
総括すると、みずほルートを使うにはJQ CARDセゾンとみずほマイレージクラブカード/ANAの2枚が不可欠であり、それぞれの年会費や初期設定をしっかり確認しておくことが成功のカギです。
TOKYUルートに慣れていた人にとってはステップ数が増えますが、ウェブ完結かつ70%の還元率を維持できるのは大きな魅力。次のセクションでは、みずほルートに対応しているポイントサイトの選び方や、VポイントやGポイントを使って70%還元を維持する方法について紹介します。
みずほルート対応のポイントサイト選び

みずほルートを使ってANAマイルを効率よく貯めるためには、まずポイントサイトで得たポイントをVポイント(旧Tポイント)やGポイントに交換できるかどうかが重要です。
なぜなら、みずほルートではVポイント(もしくはGポイント)に交換してからJRキューポ→永久不滅ポイント→ANAマイルという流れを辿るため、ポイントサイト側でVポイント(またはGポイント)へ変換する機能がないと高還元率を維持できないからです。
大手ポイントサイトの多くはVポイントへ直接交換できるケースが増えてきましたが、サイトによってはGポイントを経由しないと最終的にVポイントにできないものもあるので注意が必要です。
また、そもそも特定のポイントサイトでは還元率が低い商品やサービスばかり取り扱っていて、貯まりにくいという場合もあります。みずほルートを成功させるには「獲得しやすい案件」と「高還元率」がそろったポイントサイトを選ぶと効果的です。
具体的には、ハピタスやモッピーなどはユーザーが多く、クレジットカード発行や銀行口座開設、FX口座など高額案件が揃っているため、短期間で大量のポイントを稼ぎやすい傾向があります。一方、ドットマネーやPexといったポイント交換サイトを必ず経由しなければいけない場合もあるため、自分がメインで使うポイントサイトと交換サイトの対応状況を事前に確認しましょう。
みずほルートの場合、TOKYUルートのように交換機器を使った地域限定の手続きは一切なく、すべてウェブ上で完結できる点が魅力ですが、複数回のポイント交換を行うことになるため、交換時期や手数料が変わる場合がある点にも留意してください。
とくに、Vポイントへの変換時やJRキューポへの移行時にはサイト側で定めるレートや交換期限が設けられることがあります。小まめにサイトのお知らせやキャンペーン情報をチェックし、レートダウンや手数料増加といった不測の事態に備えるのがおすすめです。
さらに、みずほルートを長期的に使い続けるには、ポイントサイトでの獲得案件が安定していることも大切です。高額案件(クレジットカード発行など)を一定期間で利用し尽くしてしまうと、新規にポイントを集める手段が乏しくなりがちです。
そこで、商品購入やサービス利用で定期的にコツコツとポイントを積み重ねられるサイトかどうかも選定の基準に入れましょう。次の見出しでは、特にVポイント(旧Tポイント)・Gポイントを使いこなし、70%の高還元率を維持するための具体的な方法について掘り下げます。
Vポイント(旧Tポイント)・Gポイントで70%を維持する方法
みずほルートでは、ポイントサイトのポイントをVポイント(旧Tポイント)またはGポイントへ交換し、そこからJRキューポ→永久不滅ポイント→ANAマイルという流れを踏むことで、還元率70%を実現します。このステップを正しく踏むためには、いくつかの工夫や注意が必要です。以下に代表的な方法とポイントを挙げてみましょう。
まず、Vポイントへの交換がスムーズに行えるポイントサイトを活用することが大切です。最近ではVポイント移行対応のサイトが増えていますが、一部のサイトでは直接Vポイントに変換できず、Gポイントなどを経由しないといけないケースもあります。
たとえば、ハピタスなら直接Vポイントへ交換できる場合がありますが、モッピーやポイントインカムではドットマネーやPeXなどを間に挟む必要がある、といった形です。こうした移行ルートの違いを踏まえ、どのサイトをメインの稼ぎ先とするかを決めると交換時の手間が減ります。
次に、Gポイントを選択する方法も有効です。GポイントもJRキューポへの移行が可能で、結果としてANAマイル70%還元のルートに乗せることができます。ただし、Gポイントの場合はサイトによって還元レートや交換制限が異なることがあるため、Vポイントへの直接交換が難しいポイントサイトを使っている人が代わりに活用する、といった役割を担うことが多いです。
- ポイントサイトの交換メニューでVポイント(or Gポイント)が選べるか確認
- 一部サイトではポイント交換サイト(ドットマネーやPeX)を経由しないとVポイントへ移行できない場合がある
- VポイントやGポイントへの交換レート・手数料に変動がないか定期的にチェック
また、Vポイントに交換したあとも、JRキューポ→永久不滅ポイント(JQ CARDセゾン必須)→ANAマイル(みずほマイレージクラブカード必須)という手順を踏むことを忘れないようにしましょう。ここでどこか1つでも手続きを間違えると、70%の還元率を達成できない可能性があります。
たとえば、Vポイントから別のルートに移行してしまうとレートが下がったり、交換ルートをショートカットしようとしてみずほルートを外れてしまうと還元率が大幅に落ちたりする恐れがあるのです。
最後に、VポイントやGポイントに交換するタイミングをまとめ買いや大型案件が多い月に合わせると、一度に大量のポイントを移行できて効率がいいでしょう。
ただし、キャンペーンで交換レートが一時的にアップする場合もあるため、サイト側のイベントやお知らせを確認する習慣をつければ、さらにお得にVポイント・Gポイントへ移行できます。次の見出しでは、もしVポイントへの交換ができないポイントサイトを使っている場合にどう対処すればよいのか、具体的な方法を紹介します。
Vポイントへの交換ができない場合の対処法
ポイントサイトによっては、Vポイント(旧Tポイント)への直接交換に対応していない場合があります。特に、近年はVポイントと提携を強化しているサイトが増えているとはいえ、まだすべてのサイトが対応しているわけではありません。
そのため「普段よく使うポイントサイトがVポイント交換に対応していない」という陸マイラーも少なくありません。そんなときに使える方法としては、以下のような対処法が考えられます。
- ポイント交換サイト(ドットマネー、PeXなど)を経由する
Vポイントへ直接交換できなくても、ドットマネーやPeXなどのポイント交換サイトでいったん別のポイント(例:ドットマネー)に変換し、そこからVポイント(またはGポイント)へさらに移行する二段階の方法があります。手数料やレートが変化する可能性があるため、交換内容を事前にチェックしながら進めるのがおすすめです。 - Gポイントに変換してJRキューポ→永久不滅ポイントへ進む
Vポイントが無理ならGポイントという選択肢もあります。GポイントもJRキューポへの変換が可能なので、結果的にみずほルートへ合流することができます。ただし、Gポイント自体に交換手数料が設定されている場合や、移行レートが変動する場合があるため、常に最新の情報を確認しておきましょう。 - 別のポイントサイトをメインにする
あまりにも複雑になるなら、Vポイント交換に対応しているポイントサイトを新たにメインとする方法も一案です。ハピタスやモッピーなど、有名どころのサイトはだいたいVポイント移行に対応しつつ高還元案件が揃っていることが多いため、切り替えを考えてみる価値があるでしょう。
- 交換サイトを経由するときはレートや手数料が変わらないか事前に確認
- キャンペーン期間中はレートアップや手数料無料になるケースがある
- 煩雑すぎると管理しきれなくなるため、別サイトへの乗り換えも検討
また、どうしてもVポイントへの移行が難しいなら、ほかにGポイントやTポイント(旧Tポイント)系のルートを持つ交換方法を探すことも必要です。
みずほルートを70%還元で実行するには、JRキューポと永久不滅ポイントを経由するフローがほぼ固定されているため、どれかの段階でショートカットしようとすると還元率が低くなります。結果として、TOKYUルートが廃止された後に一番汎用性が高いのはVポイントへの交換が可能なポイントサイトを活用する形、といえるわけです。
総括すると、Vポイント未対応サイトを愛用している場合はポイント交換サイトやGポイントをうまく使うことでみずほルートに合流できますが、手数やレートを考慮したうえで、長期的な運用に無理があるならメインサイトを変える勇気も必要です。
次の見出しでは、みずほルートを長期的に活用するためのテクニックを紹介し、どのように交換時期やまとめ買いを計画すればANAマイル獲得を最大化できるかを解説します。
みずほルートを長期的に活用するコツ
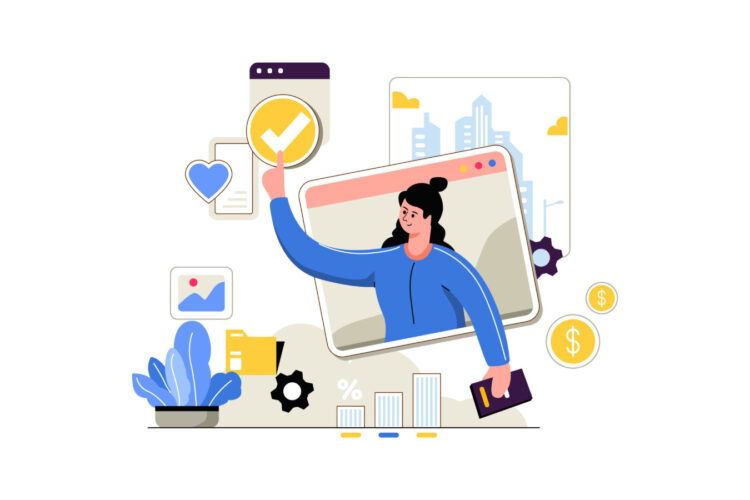
みずほルートは、TOKYUルート廃止後も高還元率(70%)でANAマイルを貯められる数少ない選択肢として注目されていますが、長期的に利用するには「交換のタイミングや支払いのまとめ方」を意識しながら、無理のないペースでポイントを管理していくことが大切です。
還元率の高さを活かそうと、むやみにポイント交換の頻度を上げてしまうとサイトごとのレート変更や手数料が発生し、思ったほどポイントが貯まらなかったり、煩雑な手続きで挫折してしまうリスクがあります。
そこで、年間や月間などある程度のスパンで交換計画を立て、ポイントが一定量以上貯まったタイミングでまとめてVポイント(旧Tポイント)またはGポイントに移行する方法がおすすめです。
複数の交換ステップを一度に進めれば、都度レート確認する手間を減らせるうえ、大型キャンペーンやポイントアップデーに合わせて交換すると、思わぬボーナスが得られる可能性もあります。
また、ポイントサイトで貯めたポイントをただ放置せず、期限切れやレート変更が起こる前に計画的に交換することも重要です。特にキャンペーン時期にはレートが上がったり交換手数料が無料になったりすることがあるため、そうしたチャンスを見逃さずチェックしておきましょう。
定期おトク便やサブスク費用など、月々固定で発生する支出をクレジットカード決済に集約しておけば、自然とポイントサイト案件(クレカ発行や各種キャンペーン)との相乗効果でポイントが貯まるペースを維持できます。また、家族やパートナーとも協力してポイントサイトを使うと、一度の買い物案件でも倍以上のポイントを稼ぎやすくなり、みずほルートへの移行回数もまとめやすくなります。
加えて、nimocaルートと比較してみずほルートを選んだ人は、地理的な制約なしにWeb上で完結できるメリットを最大限活かすのが長期利用のコツです。交換機に足を運ぶ必要がないぶん、ポイントが溜まったタイミングを任意に選びやすく、自分の生活リズムに合わせて「今月はポイントが○○円相当貯まったから交換しよう」と柔軟に動けます。
ただし、JQ CARD セゾンやみずほマイレージクラブカード/ANAは、年1回以上の利用や連携設定などの条件があるため、定期的にカードを使って年会費無料の状態を維持し、ANAマイレージクラブへの移行がスムーズに行えるかを確認しておきましょう。
- 月単位や四半期単位など、ある程度のペースでポイントサイトの残高をチェック
- 還元率アップや手数料無料のキャンペーン時に集中して交換する
- 家族やパートナーとポイント情報を共有し、案件の取りこぼしを減らす
- JQ CARD セゾン・みずほマイレージクラブカード/ANAの条件を満たし続ける
このように、みずほルートはTOKYUルートのように短い手順で75%還元できるわけではないものの、全国どこでも利用しやすく、地理的な制約なく70%の還元率をキープできる堅実さが魅力といえます。
次の見出しでは、TOKYUルートから移行する人がスムーズに陸マイラーライフを継続するためのポイントを紹介し、TOKYUルートとみずほルートの違いに慣れるコツなどを解説します。
TOKYUルートから移行しながら陸マイラーライフを継続
TOKYUルート廃止により、75%還元という魅力的な交換レートが失われたことは多くの陸マイラーにとって大きな衝撃でした。既にTOKYUルートを活用していた人は、路線変更を余儀なくされ、次のルートとしてみずほルートを検討するケースが多いでしょう。
還元率こそ70%に下がってしまいますが、交換機を使わずにWeb上で手続きが完結するうえ、全国どこでも利用可能という汎用性の高さを考えれば、TOKYUルートの代替として十分に実用的な選択肢といえます。ただし、移行にあたってはいくつかのポイントを押さえておくとよりスムーズに陸マイラーライフを継続できます。
まず、TOKYUルートとの大きな違いは「必要になるカードとポイント交換ステップが増える」ことです。TOKYUルートを使っていた頃は、還元率75%を目当てに少ない手順でANAマイルにしていたかもしれません。
しかしみずほルートではVポイント(旧Tポイント)またはGポイントへの交換が前提となり、そこからJRキューポ→永久不滅ポイント→ANAマイルとステップを踏むため、都度ポイントサイトやクレジットカードの登録情報が正しく管理されているかをチェックする手間が増えます。TOKYUルートを使っていた頃よりも1〜2回多くポイント交換手続きをするイメージが必要です。
加えて、JQ CARD セゾンとみずほマイレージクラブカード/ANAが新たに必要になる場合は、カード発行にかかる審査や年会費の条件を確認しましょう。
年1回の利用で年会費が無料になるJQ CARD セゾンなどはメリットが大きいものの、まったく使わないままだと年会費が発生するリスクがあります。みずほマイレージクラブカード/ANAは年会費が無料ですが、ANAマイレージクラブとの連携設定が必須なため、初期登録を忘れないように注意しましょう。
また、TOKYUルートとは違い、みずほルートでは交換機や特定地域に出向く必要がない点が大きな違いです。TOKYUルート時代に地理的制限を感じずスムーズに利用できていた人は少し戸惑うかもしれませんが、Web完結の手軽さはnimocaルートよりも優れているため、新しいルートに慣れてしまえばTOKYUルートと大きな違いは感じにくくなるでしょう
。還元率が5%減ったことは残念ですが、逆に考えればWebで完結できるメリットや日本全国対応の汎用性によって、TOKYUルート時代にはなかった柔軟性を得られるとも言えます。
- VポイントやGポイントへの交換フローを理解し、交換サイト(ドットマネーなど)が必要かどうか確認する
- JQ CARD セゾン・みずほマイレージクラブカードの発行&設定を早めに済ませる
- ポイント残高が中途半端になった場合は他ポイントサービスへの併用も検討
こうした点に気をつけながら手続きを進めれば、TOKYUルートからの移行でも大きく困ることなく、陸マイラーライフを継続できます。
還元率が75%から70%へ下がったのは悔やまれるものの、依然としてみずほルートは高水準の還元率を維持しており、全国対応かつWeb完結型という特徴を持つため、TOKYUルート廃止後の代替策としては最良の選択肢のひとつと言えるでしょう。
まとめ
TOKYUルート廃止後も、みずほルートなら還元率70%でANAマイルを貯められると分かれば、陸マイラーとしての活動を続ける大きなモチベーションになります。必要なクレジットカードの年会費は実質無料に抑えやすく、地理的な制限もなくウェブだけで手続きが完結する点はnimocaルートを上回る利便性です。
各ポイントサイトからVポイント(旧Tポイント)やGポイントに交換してJRキューポ→永久不滅ポイント→ANAマイルという流れさえ把握すれば、TOKYUルートほどではないにせよ、安定的かつ高還元なマイル獲得が可能。ぜひこのみずほルートを使いこなし、引き続き陸マイラーライフを満喫してみてください。